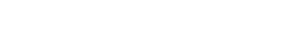スマートフォンの普及により、誰しもが日常的に使うようになったアプリ。近年は、社内の情報共有・コミュニケーションにもアプリを活用する企業が増えています。その目的は、業務効率化やナレッジシェア、社員のエンゲージメント向上や、従業員体験(エンプロイーエクスペリエンス)改善などさまざま。
本記事では、いま注目の社内アプリについて基礎から解説します。
目次
社内コミュニケーションの課題
社内アプリの導入が広がる背景には、企業がかかえる「社内コミュニケーションの課題」があります。誰しも「コミュニケーションが重要」と考えますが、実際にはさまざまな課題が発生しています。代表的な課題を見ていきましょう。
各部門や事業所同士のコミュニケーション不足
同じ部署であれば、会議などで頻繁にコミュニケーションをとる機会がありますが、別の部署のメンバーとの場合はいかがでしょうか? また、全国に事業所がある場合、なかなか一箇所に集まってコミュニケーションを取ることは少ないでしょう。仮に情報をメールで一斉送信したとしても、見落とされるケースも。
また、リモートワークを推進したことで、同じチーム内でも雑談などの「ちょっとした会話」の量が不足しているとの課題が出てきています。
ナレッジが共有されず、非効率な業務が発生している
個々人の知識(ナレッジ)をきちんと共有しないと、業務が属人化します。担当者が異動や転職になると、どこに情報があるのかわからないという問題が発生してしまいます。
また、他の担当者の業務進捗が見えないことで、やるべき作業が抜け落ちたり、逆に重複したりと、非効率な業務が発生することもあります。
電話や会議に無駄な時間・コストがかかる
内線電話でコミュニケーションを取るのは、どんどん非効率になっています。電話を受けた側は業務を中断する必要がありますし、常に自席にいるとは限らないので別の人が電話を受け、要件をメモしたり、折り返しの電話を行ったり……。
また、会議、とりわけ大人数の社員が参加する会議では、会場準備や交通費、参加者の時間など、大小ざまざまなコストが発生します。
経営陣のメッセージが伝わらない
企業間の競争が激しくなっているいま、経営者のビジョン、会社の向かう先を全従業員に伝える重要性が増しています。これらのメッセージは、一度伝えただけではなかなか浸透しないため、繰り返しコミュニケーションを取る必要がありますが、従業員に届かない、理解されないという課題があります。
社内報が読まれない
社内のできごとや、連絡事項を伝えるインナーコミュニケーションの手段として、社内報を活用している企業もあります。ところが、社内報制作は労力がかかるわりに、ちゃんと読まれているのか、内容が理解されているのかがわかりづらいという問題があります。
企業と従業員のエンゲージメントを作るためのGuide Book!
 働き方や仕事における価値観が変化している昨今において、従業員が自身の日々の仕事に満足できるような体験を提供することで、組織エンゲージメントを高める方法について丁寧に解説。組織エンゲージメントの向上はなぜ近年、そして今後より大切になっていくのかや、アプリなどのデジタルツールを活用して、従業員の業務を効果的にサポートする方法などを紹介します。
働き方や仕事における価値観が変化している昨今において、従業員が自身の日々の仕事に満足できるような体験を提供することで、組織エンゲージメントを高める方法について丁寧に解説。組織エンゲージメントの向上はなぜ近年、そして今後より大切になっていくのかや、アプリなどのデジタルツールを活用して、従業員の業務を効果的にサポートする方法などを紹介します。
コミュニケーション課題を解決するツール
こうした課題を解決するために、電話やメールに代わる様々な新しいツール・ソフトウェアが登場しています。以下、お互いに機能が重複する部分もありますが、代表的なツールについて紹介します。
ビジネスチャットツール
ビジネスチャットツールとは、その名の通りメンバー間でチャットを行うことができるツールです。「Slack」「Chatwork」「LINE WORKS」などのサービスが有名で、いまや社内外問わず、メールではなくチャットツールを用いてコミュ二ケーションをとっている企業も多いのではないでしょうか。
グループウェア
グループウェアとは、社内の情報共有を目的として導入されるソフトウェアです。スケジュール管理やTodoの共有、ドキュメントの掲載、ワークフローなど、情報共有のためのハブとして活用されています。
社内SNS
社内SNSとは、企業向けに開発されたSNSです。メッセージを送ったり、タイムラインへ投稿したりと、プライベートで使用するSNSと同じ感覚で利用できることから、導入が広がっています。既読有無の確認ができたり、社内SNS上でタスク管理を行って業務の進捗状況を共有したりと、機能次第でできることがたくさんあります。
社内SNSについて詳しく知りたい方は、下記の記事がおすすめです。
社内アプリ
社内アプリとは、社内のコミュニケーション・情報共有のために自社開発したスマートフォンアプリです。自社商品・サービスの情報や、社員研修の内容、社内報などを掲載し、従業員に向けて発信します。掲載する情報を見やすく整理して表示することができます。社内アプリでの情報共有は比較的新しい手段となりますが、チャットツールやグループウェアで生まれた新たな課題も解決できるツールとして注目を集めています。
それでは、ここからは本題である社内アプリについて詳しく見ていきましょう。
組織エンゲージメント向上にスマートフォンアプリがおすすめな理由を解説
 組織エンゲージメントの向上は企業の重要課題です。本ホワイトペーパーでは、スマートフォンアプリを活用した組織エンゲージメントの効果的な向上施策について解説します。
組織エンゲージメントの向上は企業の重要課題です。本ホワイトペーパーでは、スマートフォンアプリを活用した組織エンゲージメントの効果的な向上施策について解説します。
社内情報アクセスの改善や全国の従業員とのコミュニケーション強化に悩む企業の方々に、おすすめの内容です。。
社内アプリの主な機能
社内のコミュニケーション課題を解決するために、導入が進む社内アプリ。ここでは、具体的にどのような機能が活用できるのか見ていきます。
研修資料閲覧
研修資料やマニュアルを電子化して、アプリ内で閲覧できるようにする機能です。検索機能を使用すれば、過去の資料にも簡単にアクセスできます。特にスキル向上を目的とした研修の場合、内容がなかなか定着せず、業務で忙しいなか学習時間を確保するのも難しいことがあります。アプリで気軽に閲覧できるようにすることで、隙間時間での学習が可能になります。
動画機能
文章だけでは伝わりづらい情報は、動画で共有することで理解が深まります。YouTubeなどの動画サービスと連携して、アプリ内に動画を掲載することができます。
また、企業理念や事業戦略など、「社長メッセージ」を動画で全従業員に届けることで、理念浸透をサポートします。
社内報閲覧
社内報を紙で配布している場合、それを電子化して、全従業員に配信できます。更新時にはプッシュ通知で告知ができるため、閲覧してもらえる可能性が高まります。また、過去の社内報をアーカイブできるため、中途社員が遡って情報に触れ、キャッチアップすることができます。
社内ポータル
就業規則や組織図、人事発令など、ふとしたときに必要となる情報もアプリに集約することができます。探す手間が減り、「この情報はどこにあるのか?」といった問い合わせも減らすことができます。
コンテンツの出し分け機能
コンテンツの内容によっては、雇用形態や役職によって閲覧範囲を制限したい場合もあるでしょう。また、全国に支店がある場合、地域によって必要な情報が異なることも。出し分け機能を使うことで、ユーザーごとに必要な情報だけを表示できます。
【社内アプリの成功事例】「情報の格差」を解消して、平等な情報伝達を実現!
 約2.1万人の従業員を持つヤンマーホールディングスが、企業価値観「HANASAKA」浸透のためのアプリを導入。4コマ漫画や動画など気軽に楽しめるコンテンツで、社用端末を持たない従業員も含めた情報格差の解消と、部門・国境を越えたつながりを創出。8割以上が好評価を示すなど、新しい社内コミュニケーション基盤として成果を上げています。
約2.1万人の従業員を持つヤンマーホールディングスが、企業価値観「HANASAKA」浸透のためのアプリを導入。4コマ漫画や動画など気軽に楽しめるコンテンツで、社用端末を持たない従業員も含めた情報格差の解消と、部門・国境を越えたつながりを創出。8割以上が好評価を示すなど、新しい社内コミュニケーション基盤として成果を上げています。
社内アプリのトレンドと最新動向
ハイブリッドワーク時代の社内アプリの役割
2023年以降、コロナ後のハイブリッドワークが定着し、社内アプリの役割も大きく変化しています。現在のハイブリッドワーク環境では、オフィスワークとリモートワークを併用する従業員が増加しており、場所や時間を問わず一貫した情報アクセスを提供する社内アプリの重要性が高まっています。
最新の調査によると、2024年には日本企業の約65%がハイブリッドワークモデルを採用し、従業員の約70%がモバイルデバイスから社内システムにアクセスしていることがわかっています。このような環境下で、社内アプリはオフィスと自宅をつなぐ「デジタルブリッジ」としての役割を担っています。
AI機能の統合
2024年以降、社内アプリに生成AIを統合する企業が急増しています。具体的な活用例としては以下のようなものがあります:
- AIアシスタントによる情報検索: 膨大な社内ドキュメントから瞬時に必要な情報を抽出
- 社内FAQチャットボット: 人事制度や社内規則に関する質問に24時間自動回答
- 会議議事録の自動生成: 会議の音声を自動的にテキスト化し、要点をまとめる機能
- 業務フローの自動化推奨: 日常業務の効率化につながる自動化提案を行う機能
これらのAI機能により、情報へのアクセス性が飛躍的に向上し、社員の生産性向上にも大きく貢献しています。最新調査では、AI機能を搭載した社内アプリを導入した企業では、従業員の情報検索時間が平均40%削減されたという結果も出ています。
社内アプリ導入4つのメリット
それでは、これらの機能を備えた社内アプリの導入によって、企業にはどんなメリットがあるのでしょうか?
すべての情報を集約できる
社内アプリはストック型の情報集約ツールです。フロー型のチャットツールだと情報が流れてしまいますし、ファイル共有システムだとルールを厳密に運用しない限り情報が散在してしまうデメリットがあります。社内アプリであれば、「ここさえ見ておけば安心」と言うことができます。
プッシュ通知で情報をリアルタイムに届ける
情報を更新しても、それを全従業員に周知するのは意外と大変です。プッシュ通知を使うことで、更新をリアルタイムで伝えることができます。また、アプリのプッシュ通知は、メルマガと比べて開封率が高いと言われています。従業員がアプリを起動していなくてもロック画面にメッセージを表示できるので、見落とされてしまうことがなくなります。
自由自在なデザインでエンゲージメント強化
グループウェアや社内SNSは、サービスを提供する企業がデザインをコントロールします。社内アプリを自社開発した場合、デザインは企業のコーポレートカラーに合わせて自由に設定が可能です。また、スマートフォンのホーム画面に自社のロゴを入れたアイコンを表示できるので、従業員の企業へのエンゲージメントを向上させることができます。
社内の関係者だけが閲覧・編集できる
さきほど、従業員ごとの情報の出し分けについて触れましたが、前提として社内アプリに掲載するコンテンツは社内限定のもの。そのため、社内の関係者だけしかアクセスできないよう、セキュリティ設定が重要になります。一般的なスマートフォンアプリは、App Store、Google Playといったアプリストアに公開しますが、社内アプリは一般公開されない専用ストアからクローズな方法で配布が可能です。
自社アプリの導入について知りたい方へのプレゼント!
「そもそもアプリ開発ってどうやって進めるの?」と疑問に思った方にぜひ読んでいただきたいのが、全6ステップに分けてアプリ開発の流れを平易な言葉で解説した無料eBook。ちょっとしたスキマ時間で気軽に見れるボリュームなので、ぜひ一度ご覧になってみてください!
社内アプリの注意点
ここまで主に社内アプリのメリットについて述べてきましたが、導入にあたってはいくつか注意すべきポイントがあります。
業務時間外の使用
社内アプリの魅力は、従業員にとって身近なスマートフォンから簡単にアクセスできることですが、同時に業務時間外にも閲覧できてしまいます。これを負担に感じる従業員もいるでしょう。業務時間外に、アプリを閲覧しなくても良いように、運用ルールを定める必要があります。
導入・運用コストがかかる
アプリを開発するためには、導入コストや運用コストが発生します。料金体系や機能にもよるため、チャットツールやグループウェアなどと単純に比較はできませんが、自社オリジナルのソフトウェアを導入することになるため、一定のコストが発生することを念頭に入れておく必要があります。
近年では、ノーコードと言われる、プログラミング不要で簡単にアプリを作ることができるサービスも登場しています。このようなサービスを活用すれば、コスト負担をある程度抑えることが可能です。
情報漏洩・セキュリティリスク
ソフトウェア導入により、情報漏洩リスクや情報マネジメントの工数が発生します。社内アプリに掲載する情報は、社内の従業員だけにしか共有したくないものも多く存在するでしょう。退職者管理を行って、社外の人が閲覧できないようにするためには、セキュリティ対策が欠かせません。また、情報の種類によっては、特定の従業員にだけ共有したい場合もあるでしょう。
前述のように、アプリの配布方法によっては、こうした問題にスムーズに対応することも可能なので、開発会社に相談してみると良いでしょう。
セキュリティと法令遵守の進化
ゼロトラストセキュリティの導入
2024年以降、「ゼロトラスト」の考え方に基づいたセキュリティ対策が社内アプリにも適用されています。従来の「社内ネットワークは安全」という前提を捨て、すべてのアクセスを検証する方針が主流になっています。
具体的には、以下のようなセキュリティ機能が標準となっています:
- コンテキストベースのアクセス制御: 利用端末、ネットワーク環境、時間帯、位置情報などの要素に基づく動的なアクセス権限の付与
- マイクロセグメンテーション: 情報を細かく区分し、必要最小限のアクセス権のみを付与
- 継続的認証: セッション中も定期的に認証を確認し、不正アクセスのリスクを低減
プライバシー保護とGDPR対応
従業員データのプライバシー保護が世界的に強化される中、社内アプリも対応を進めています:
- データ最小化: 業務に必要な最小限のデータのみを収集・保存
- 利用目的の明示: データ収集の目的を明確に提示
- データポータビリティ: 従業員が自身のデータを取得・移行できる仕組み
- 忘れられる権利: 退職時などにデータを完全に削除できる仕組み
特に、グローバル企業では日本の個人情報保護法だけでなく、EUのGDPRやカリフォルニア州のCCPAなど、世界各国の法令に準拠した設計が求められています。
社内アプリの活用事例
それでは、社内アプリ導入の具体的イメージをつかむために、活用事例を紹介します。
アパレル企業A社
小売店・ECそれぞれでアパレル販売を手がけるA社。顧客に向けた店舗アプリをすでに運用していましたが、社内の情報共有に課題を感じ、自社の従業員のための社内アプリを導入しました。
アパレル企業は、シーズンごとにコンセプトや商品、スタイリングの方向性が変わっていきます。A社では、こういった情報を会議で伝達していましたが、店舗スタッフも含めた全社員が参加するのは難しく、現場まで情報を浸透させることが難しかったそうです。
そこで、これらの情報を社内アプリで共有、店舗スタッフも含めた全社員がダウンロードすることで、情報を伝えることが可能になりました。
化粧品メーカーB社
化粧品メーカーのB社には、店舗で顧客に商品知識を伝え、生活の場で役に立つアドバイスを行うスタッフがいます。新商品が頻繁に入れ替わるなか、顧客に正しい情報を伝えるために、情報共有にスピード感が求められていました。
以前は、本社社員が全国の支店に出張して講習会を開いたり、逆に代表者を一箇所に集めて集合研修を行っていましたが、手間やコストがかかるため、代替手段として社内アプリを導入しました。
スマートフォンに最適化された形で商品情報を見やすく整理してアプリで表示、店舗スタッフは欲しい情報へすぐにアクセスできるようになりました。ペーパーレス化を実現し、一人ひとりの手元にあるスマートフォンから情報が閲覧できるようになったことで、アプリの利用率は高水準を達成。店舗を訪れる顧客へ、最新の情報を的確に伝えることが可能になりました。社内の情報共有課題を解決したことで、接客の質も向上した事例になります。
最新の活用事例
製造業C社:現場DXの実現
製造業のC社は、2023年に社内アプリを導入し、工場の現場作業と管理部門をシームレスにつなぐことに成功しました。従来は紙の報告書や専用端末での入力が必要だった作業報告を、現場作業員のスマートフォンから直接入力できるようにしたことで、データ入力の時間を1日あたり平均45分短縮。また、不良品発生時の報告から対応までのリードタイムを80%削減することに成功しました。
アプリ内にAR(拡張現実)機能を搭載し、複雑な機械の保守点検手順をビジュアル化したことで、新人教育の効率も大幅に向上しています。
金融機関D社:リモートワーク時代の社内コミュニケーション強化
金融機関のD社は、2024年に導入した社内アプリによって、ハイブリッドワーク環境下での社内コミュニケーションを強化しました。特に注目されるのは、AIを活用した「関心ベースマッチング」機能です。従業員のプロフィール情報や投稿内容から関心領域を分析し、類似の興味を持つ社員同士をつなげる仕組みを構築。部署や役職を超えた新たなつながりを生み出すことで、イノベーションの創出につながっています。
また、経営陣による動画メッセージの視聴率は従来の社内報の4倍に達し、従業員エンゲージメントスコアも25%向上しました。
まとめ
社内アプリは、単なる情報共有ツールから、ハイブリッドワーク環境での「デジタルワークプレイス」の中核へと進化しています。AI機能の統合、従業員ウェルビーイングの支援、高度なセキュリティ対応など、その機能は年々拡充されています。
特に人的資本経営が注目される中、従業員体験(EX)の向上と業務効率化の両立を実現する社内アプリの需要は今後もさらに高まるでしょう。
社内アプリ導入を検討する際は、単なる情報共有にとどまらず、従業員の働き方や組織文化をいかに進化させるかという視点で戦略を立てることが重要です。ツールの導入自体が目的ではなく、それによって実現したい組織変革のビジョンを明確にした上で、適切な機能設計と運用計画を策定することをおすすめします。
本メディアを運営する株式会社ヤプリは、企業のDXを推進するために、社内アプリの活用を積極的に支援しています。社内アプリで従業員エンゲージメントを強化するためのサービス「Yappli UNITE(ヤプリユナイト)」の導入実績も豊富です。
社内アプリ開発に興味を持たれた方は、ぜひ一度、ヤプリまで資料請求してください。