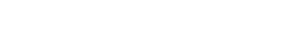販売やマーケティングに携わっている方なら、「販売促進(販促)」という言葉を日常的に使っているのではないでしょうか。しかし、あらためて「販売促進の定義や目的は何か?」と聞かれると、明確に説明するのは難しいかもしれません。
今回は、販売促進の概要や目的のほか、種類、具体的な手順などについて詳しく解説します。また、宣伝、マーケティング、営業との違いや、オフラインチャネルとオンラインチャネルの特徴などもひとつずつ押さえていきましょう
目次
販売促進とは、購買意欲を刺激して購買行動へとつなげる活動の総称
販売促進とは、消費者の購買意欲を刺激して購買行動へとつなげる活動の総称です。セールスプロモーションという言葉が使われることもありますが、それも販売促進とほぼ同じ意味を表していると捉えてください。
例えば、自社商品を知ってもらうために広告を打ったり、キャンペーン企画を打ったりすることも販売促進に含まれます。また、DMの送付やSNSを活用したプロモーションなども販売促進の一種です。このように、販売促進は「買ってもらうための働きかけ」を包括的に表しているのです。
販売促進の方法を検討する中で、近年注目度が高まっているのが「自社アプリ」の活用です。
本資料ではアプリを活用することで販売促進につなげる具体的な方法を、事例と併せて紹介しています。ちょっとしたスキマ時間で気軽に見れるボリュームなので、ぜひ一度ご覧になってみてください!
販売促進と宣伝・マーケティング・営業との違い
販売促進は商品を売る行為として、そのほかの活動といっしょにくくられてしまうこともありますが、それは誤りです。ここでは、販売促進と宣伝・マーケティング・営業との違いについて具体的に押さえていきましょう。
宣伝との違い
自社や商品について知ってもらうための宣伝は、販売促進の具体的な活動のひとつです。宣伝は、広告や店頭での呼び込みなどを通じて商品を売るための活動であり、販売促進を実現するための手段といえます。
マーケティングとの違い
マーケティングは「売るための仕組み」の構築を指す言葉です。売るための仕組みの中には、消費者の購買意欲を刺激することを目的とした施策も含まれているでしょう。販売促進はマーケティング施策のひとつであるともいえます。
営業との違い
営業とは、消費者に商品を提案し購入を決断してもらうための後押しをする活動を指します。キャンペーン企画を通して商品を広く知ってもらう中で、商品に興味を持ち購入を検討する層は一定数現れることでしょう。そこで、消費者に購入を決断してもらうために、背中を押す一言が必要になることがあります。
たとえ、優れた販売促進戦略を打ち出したとしても、実際に買ってもらうには説得や後押しが不可欠となることが少なくありません。営業とは、販売促進を成功させるための具体的な活動のひとつであり、購入意思の最終決定を後押しする役割を担っているのです。
販売促進の目的とは?
販売促進には、大きく分けて3つの目的があります。目的に応じて販売促進の手法や進め方は異なる場合もあるため、何をゴールとして取り組むのかを理解しておくことが大切です。
プロモーション活動の具体例
プロモーション活動には多くの方法がありますが、代表的なものをいくつか取り上げて説明します。まず、クーポンや割引キャンペーンは効果的な手段です。クーポンを利用することで、消費者は通常よりも安価に商品を購入できるため、購入の動機付けとなります。
サンプル配布も有力な方法のひとつです。新商品や改良品のサンプルを提供することで、消費者に実際に商品を試す機会を与え、品質を体感してもらうことができます。
さらに、イベントやフェアへの参加も重要です。ブランドや商品を広く知らしめるため、地域のイベントや業界フェアでの展示やデモンストレーションを行うことが有効です。これらのプロモーション活動を組み合わせることで、より効果的な販売促進が可能となります。
商品の認知度向上
商品を購入してもらうには、商品の存在そのものを知ってもらう必要があります。まだ商品の存在を知らない層にアプローチし、どのような商品なのか、具体的なメリットや長所を含めて伝えていくのが販売促進の重要な目的のひとつです。
商品の認知度を向上させるための戦略や活動は、新規顧客を獲得する上で欠かせません。商品に興味を持ってもらえるようターゲットを幅広く設定することもあれば、特定の属性や購買行動に合致する層へ集中的にアプローチすることもあります。例えば、商品を紹介する広告や店頭での商品紹介のほか、WebサイトやSNSを活用した商品の告知なども認知度を高めるための戦略の一つです。
購入・消費の促進
商品を認識した消費者は、対象の商品を必ず購入するとは限りません。消費者は自分にとってその商品は購入するメリットがあるのか、他社商品よりも優れているのかといった点を検討した上で購入するか否かを決めるからです。
そこで、購入に対する心理的なハードルを下げるために割引クーポンを発行したり、ノベルティをつけてお得感を演出したりするのは、まさに販売促進のための施策といえます。また、期間限定のキャンペーンを打つことで限定性をアピールし、その場での購入の後押しをすることも販売促進の手法のひとつです。
このように、商品を認知した消費者に対して購入・消費を促すことも販売促進の目的といえるでしょう。
リピーターの創出
販売促進のターゲットとなるのは、新規顧客だけではありません。既存顧客に対してリピート購入を促すことも販売促進のひとつです。新規顧客を獲得することも、既存顧客にリピート購入を決めてもらうことも、数字上は売上への貢献度は変わりません。しかし、商品の良さをすでに実感しており、商品を提供する企業に対して信頼を寄せている既存顧客にリピート購入を検討してもらうほうが、新規顧客を獲得するよりも難度が低いケースは多いといえます。
リピーターを創出することは、継続的な売上を確保する意味でも重要な戦略となります。過去に自社商品を購入した履歴のある消費者に対してリピート購入を促し、継続的に利用してもらうよう働きかけていくことも、販売促進の大きな目的です。
販売促進のチャネルは、オフラインとオンラインに分けられる
販売促進のチャネルは、「オフラインチャネル」と「オンラインチャネル」に分けられます。ここでは、それぞれのチャネルで行われる施策について具体的に見ていきましょう。
オフラインチャネル
オフラインチャネルとは、インターネットを使用しない販売チャネルのことです。下記に挙げる施策は、いずれもオフラインチャネルによる販売促進といえます。
<オフラインチャネルの例>
- 折込チラシ
- ポスティング
- DM
- 店頭POP
- 展示会
- リアルイベント
オフラインチャネルは、古くから行われてきた販売促進のチャネルであり、業種を問わず幅広い事業者が活用しています。消費者に対して直接的に商品を訴求できることから、比較的高額の商品にはオフラインチャネルが活用されやすい傾向もあります。
一方で、オフラインチャネルは印刷費や発送費、イベント準備のための費用といったコストがかかる点には注意が必要です。さらには、折込チラシやポスティングは、配布するエリアの選定を誤れば販売促進の効果が薄れてしまうでしょう。また、DMであれば見込み顧客リストを用意する必要があるため、リストの収集に手間と時間がかかるのは避けられません。オフラインチャネルは、投じる費用や時間と得られる効果とのバランスを、十分に考慮する必要があります。
オンラインチャネル
オンラインチャネルとは、インターネットを駆使した販売チャネルのことです。オンラインチャネルの例としては、下記のようなものが挙げられます。
<オンラインチャネルの例>
- 自社Webサイト
- SNS
- メールマガジン
- リスティング広告
- 動画広告
- ランキングサイトやレビューサイト
- オンラインイベント
- アプリ
オンラインチャネルは、オフラインチャネルと比べてコストを抑えた販売促進が可能であり、オフラインと比べてより緻密なターゲティングができるため、短時間で狙った消費者に情報を確実に届けやすい点が特徴です。
また、例えばアプリを活用すれば、消費者のスマートフォンの位置情報を活用して、実店舗に近いエリアにいる人へ集中的にアプローチをすることもできます。さらに、SNSであれば短期間のうちに情報が爆発的に拡散される可能性もあることから、低コストで高い費用対効果が期待できる場合もあるのです。
販売促進の対象者層
販売促進の対象となる消費者に対しては、どの層をターゲットとするかによって販売促進の戦略が異なってきます。販売促進の対象となる消費者層は大きく3つに分けられますので、それぞれの特徴と施策のポイントを確認しておきましょう。
不特定の消費者
不特定の消費者とは、自社商品を認知していない層を指します。商品名はおろか、商品の存在そのものを知らない層のため、まずは「知ってもらう」ことが重要です。チラシやWeb広告、SNS広告などを通じて、できるだけ多くの消費者へ商品に関する情報を届けましょう。
その際、商品の詳細な説明には踏み込まず、まずは認知してもらうことを優先するのがポイントです。印象的なキャッチコピーやインパクトのあるデザインなど、多くの人の目を引くことに注力する必要があります。
見込み顧客
見込み顧客とは、商品購入を検討中の消費者や、購入する可能性が高い属性の消費者を指します。見込み顧客にアプローチする際は、自社商品の長所や、他社商品と比較した場合の優位性を強く打ち出しましょう。また、購入を決断する理由を消費者に与えておくことも重要です。
初回購入者を対象とした割引キャンペーンを打ち出したり、期間限定の割引クーポンといった優待措置を設けたりすれば、今すぐに購入するメリットを感じてもらうことができます。消費者の購買意欲を後押しし、購入を決断するという行動につなげることが大切です。
既存顧客
既存顧客とは、自社商品を過去に購入した経験がある消費者を指します。2回目以降の購入へとつながる確率は、企業側からの働きかけによって大きく変わるため、既存顧客に対しても販売促進は欠かせません。メルマガやアプリのプッシュ通知などを通じて消費者にとって有益な情報を提供し、顧客として大切にされていると実感してもらうことが大切です。
また、継続利用者を対象とした特典やポイント制度なども設け、商品を利用し続けるメリットを感じてもらうことも重要な施策のひとつといえます。既存顧客に対しては、アップセルやクロスセルにつながるよう、顧客との接点を持ち続け信頼関係を築いていくのがポイントです。
販売促進の手順
実際に販売促進に取り組む際には、どのような手順で進めればいいのでしょうか。続いては、販売促進の基本的な手順をご紹介します。
1. 市場調査を行う
初めに、販売する商品にどのようなニーズがあるのかを調査します。自社商品が現状どのように認知されており、競合他社の商品は販売状況がどうであるのか、客観的な指標をもとに分析していきます。その際、過去の売上データや顧客情報、顧客へのアンケートといった資料を準備しておくことが大切です。商品を売る側の論理で考えるのではなく、消費者のニーズに応えるためにはどんなアプローチが必要となるのか、十分に検討していきましょう。
2. 予算を設定する
販売促進には多種多様な手法がありますが、予算は手法によって変わります。例えば、不特定の消費者に向けて漫然とチラシをまいていると、広告費は膨大な金額に達してしまうでしょう。チラシの費用対効果をあらためて考慮してみると、もっと低コストで効果のある販売促進の手法が見つかるかもしれません。販売促進は、商品の売上目標と広告効果を天秤にかけ、ターゲットとする消費者に最も効果的なアプローチができる手法を絞り込んでいくことが大切です。
3. 展開計画を策定する
販売促進を実施する際は、全体的な戦略を立て、具体的にどのような経路で商品が購入に至るのかを設計することも大切です。広告を打つ場合、広告を見た消費者が次にどのような行動をとるのか、そしてその行動がどのように購入へと結びつくのか、展開計画を策定しておく必要があります。
そこでの注意点としては、「消費者にこのような行動をとってほしい」といった希望的観測にもとづくストーリーにはしないこと。あくまでも現実的な展開計画を策定することを目指し、無理のない展開計画になっているか複数人の目でチェックしましょう。
4. 改善策を提案する
販売促進の効果測定は最終段階で行うのではなく、途中の段階でも行い、随時改善していくことが大切です。当初から想定どおりに購入へとつながるケースはまれですので、カスタマージャーニーマップや顧客行動の分析ツールを利用して、客観的なデータをもとに改善策を提案しましょう。
また、販売促進が難航する原因は、ひとつだけとは限りません。世の中で注目されているトピックや競合他社の動向、天候の影響といった複合的な要因も洗い出し、その時点で最も効果が高いと考えられる改善策を講じていくこと大切です。販促効果の高かった事例は必ず共有し、よりブラッシュアップさせていくことも販売促進を成功させる上で重要なポイントです。
>>カスタマージャーニーについてより詳しく知りたい方は、下記の記事がおすすめです。
まとめ:販売促進は、オフラインとオンラインを融合しながらブラッシュアップを
販売促進は、宣伝や営業といった一つひとつの施策ではなく、消費者を購買行動へとつなげる一連の活動全体を指しています。商品の認知度向上や購入・消費の促進、リピーターの創出を実現する上で欠かせない施策となることから、オフライン・オンラインの各チャネルを融合しながらブラッシュアップしていくことが大切です。オフラインチャネルとオンラインチャネルをつなぐツールとして、アプリによる販売促進の強化は有効な施策といえます。プッシュ通知やスマートフォンの位置情報といったアプリならではの機能を活用することにより、消費者にシームレスな顧客体験を提供することができるのです。
アプリを活用した販売促進戦略に興味のある方は、ノーコードで実現可能なアプリプラットフォーム「Yappli」を試してみてはいかがでしょうか。詳細はサービス資料にて紹介していますので、ぜひダウンロードしてご一読ください。
>>Yappliの資料請求はこちら
資料請求 | アプリプラットフォーム「Yappli(ヤプリ)」
>>この記事もよく読まれています