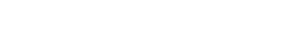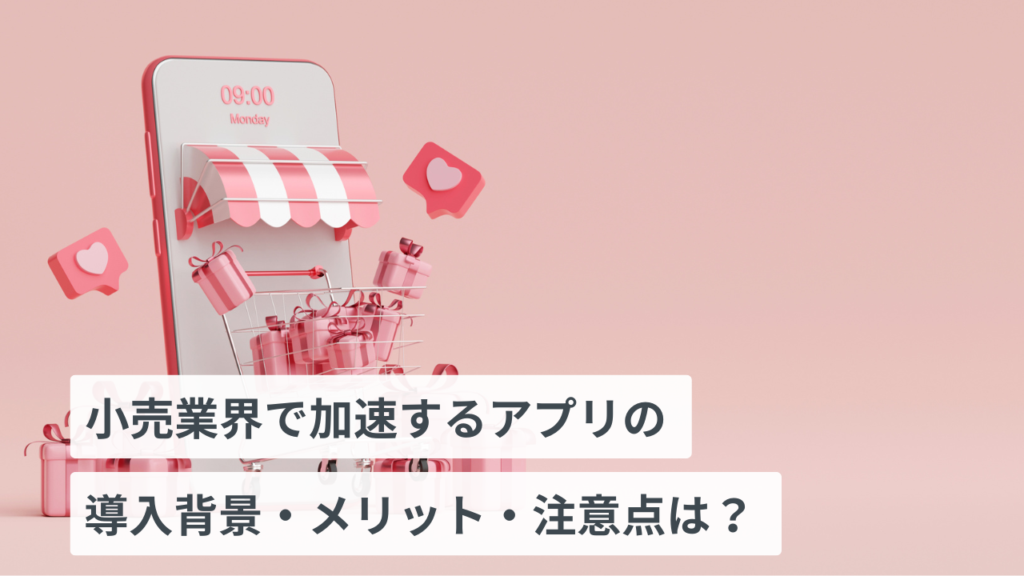
小売企業の間でアプリ導入が広がっています。この記事では、アプリが普及する背景を紹介し、アプリを導入した際に得られるメリット、及び注意点に関しても解説していきます。
目次
小売業界でますます増えるアプリの導入
日本の小売業界ではアプリの「スーパーアプリ化」が急速に進んでいます。単なるポイントカードや情報提供ツールから、決済・予約・顧客サポート・パーソナライズされたショッピング体験まで、あらゆる機能を一つのアプリに統合する動きが顕著になっています。
大手コンビニチェーンやショッピングモールのアプリは、自社ポイントシステムだけでなく、電子マネー・QRコード決済・クレジットカード連携などの多様な決済手段をサポートし、顧客の利便性を高めています。2024年のData.ai(旧App Annie)の調査によれば、日本の小売業アプリは単なる情報閲覧ツールから、実際の購買行動を完結させるプラットフォームへと進化しており、アプリ内での購買額は前年比で30%増加しています。
▷▷店舗DXを語る上で欠かせないのが顧客を軸にした購買体験を設計する「オムニチャネル」というキーワード。店舗DXへの理解を深めるために、ぜひこの記事もご覧になってみてください。
小売企業がアプリ導入によって得られるメリット
次に、小売企業がアプリを新規導入したときに得られるメリットを具体的に解説します。
ポイントカードをアプリ化できる
ポイントカードをアプリ化すると、カードの制作コストを削減しながら利用会員を増やすことができます。スマホがポイントカードの役割を持つようになるので、財布からカードを探す一手間を省けるようになり、ユーザーにとってもメリットが大きくなります。
また、ポイントアプリは住所や名前といった個人情報を入力しなくても利用可能であり、インストール直後から活用できるのも強みと言えます。実際のカードで起こりやすい紛失や劣化なども起こりづらく、誤ってアプリを削除した場合でも無料で再発行が可能です。
アプリを起動した際にログインボーナスを発行する、アプリ限定クーポンを配信するといった施策を合わせて実施すると、自然な形でリピート率を向上させやすくなります。ポイント付加は単純に値引きするよりも低コストで実施可能で、ダウンロード数増加も見込めます。そして、アプリ化することでポイント制度を手軽に利用できるようになり、競合他社との差別化や既存顧客のロイヤリティ向上といったメリットも見込めます。
▷▷【ポイントカード運用のことを知りたい方にはこちらの記事がおすすめ】
キャッシュレス決済とのポイント連携
2024年において日本のキャッシュレス決済比率は60%を超え、特にスマートフォンを介した決済が急増しています。小売アプリは単なるポイントカード代替から、複数の決済手段とポイントシステムを統合するプラットフォームへと進化しています。
多くの小売業者は自社アプリ内で、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、後払いサービスなど複数の決済オプションを提供し、さらに自社ポイントと外部ポイント(Tポイント、楽天ポイント、PayPayポイントなど)との連携も強化しています。
この「ワンストップ決済+ポイント統合」機能は、顧客の利便性を高めるだけでなく、購買データの一元管理を可能にし、より精緻なマーケティング分析の基盤となっています。2023年の調査では、複数の決済手段とポイント連携機能を備えたアプリは、そうでないアプリと比較して平均購入頻度が55%高いという結果が出ています。
ユーザーにお得な情報を提供しやすくなる
小売企業の多くは自社ホームページやメルマガ等を展開していると思われます。しかし近年は手軽なSNSが人気を集めており、閲覧までにメーラーやブラウザを経由するコンテンツは閲覧されづらい傾向があります。
スマホアプリは端末のホーム画面からワンタッチでアクセス可能なので、自社ホームページやECサイトなどへのアクセスを気軽に促すことができます。
アプリの手軽さをさらに強化する機能として、「プッシュ通知」があります。ユーザーの通信端末上に有益な情報を直接発信する機能であり、アプリやブラウザを起動していなくても確認できることが特徴です。小売企業では新製品に関する情報やクーポンなどを配信する場合が多いでしょう。
プッシュ通知は、SMSやメルマガと比べてもリアクション率が高い傾向があり、アプリの閲覧を促す方法として優れています。ユーザーの購買履歴や年齢、性別といった情報を基に通知内容をカスタマイズすることが重要なので、ショッピング機能を持たないアプリでもユーザー情報を取得するシステムを付加しておくとマーケティング精度を高めやすくなります。
そして、獲得したデータは品揃えに反映できる場合があるので、ユーザーと店側が互いに得する環境を構築していけるようになります。
販売促進の方法を検討する中で、近年注目度が高まっているのが「自社アプリ」の活用です。
本資料ではアプリを活用することで販売促進につなげる具体的な方法を、事例と併せて紹介しています。ちょっとしたスキマ時間で気軽に見れるボリュームなので、ぜひ一度ご覧になってみてください!
オフライン体験とオンライン体験の融合
先進的な小売企業は実店舗体験とデジタル体験を融合させる「フィジタル(Physical+Digital)」戦略を強化しています。店舗内でのARナビゲーション、商品のデジタル情報へのアクセス、モバイルセルフレジなど、アプリを介して実店舗での買い物体験を向上させる機能が標準となりつつあります。
特に注目すべきは「スキャン&ゴー」や「モバイルセルフレジ」機能で、顧客が商品をスマートフォンでスキャンし、レジに並ばずアプリ内で決済を完了できるシステムです。これにより待ち時間の短縮と顧客満足度の向上を同時に実現しています。2023年以降、日本の大手スーパーやドラッグストアでもこうしたシステムの導入が加速しています。
パーソナライゼーションとプライバシーの両立
2023年以降、消費者のプライバシー意識の高まりとパーソナライズされた体験への期待という、一見相反する要求に応えることが小売アプリの重要課題となっています。iOS 14.5以降のApp Tracking Transparency(ATT)やGoogleのCookieレス化などのプライバシー強化策により、従来のようなサードパーティデータに依存したマーケティングは困難になっています。
先進的な小売企業は、透明性の高いデータ収集ポリシーのもと、顧客から直接収集したファーストパーティデータを活用したパーソナライゼーション戦略を展開しています。具体的には、顧客の明示的な同意に基づく行動追跡や、匿名化されたデータ分析などを通じて、プライバシーを尊重しながらもパーソナライズされた商品レコメンドやクーポン配信を実現しています。
この新しいアプローチにより、2024年の調査では、透明性の高いデータポリシーを持つ小売アプリは顧客エンゲージメントが平均40%高く、アプリ内滞在時間も25%長いという結果が示されています。
小売企業がアプリ導入時に注意すべきこと

ここでは、小売業界の企業がアプリを導入する際に注意するべきポイント、知っておくべき知識を解説します。
運用の体制を整えておく
アプリは公開した後も定期的に更新や通知を行い、ユーザーにアプリを起動してもらう必要があります。コンテンツの更新メンテナンスには相応に高いコストや人手が必要になります。アプリを使用したユーザーから要望や不満が寄せられることも多いので、リリース後も状況に応じてデバッグが行える体制を保っておくようにしましょう。
スマホアプリの場合、iOSやAndroidといった本体OSが更新された事でアプリが起動しなくなったり、動作に不具合が出たりすることがあります。本体OSは毎年のように更新されており、修正作業が必要になった場合にはプログラムを大幅に見直すことになります。
外部企業へOSアップデート対応を依頼する場合、OS1種について150万円以上かかることが一般的です。自社で対応する場合はOS別に専属エンジニアを雇用する必要があり、いずれにしても高いコストが掛かることは把握しておきましょう。
人手不足で通知や更新を雑にしていると、ユーザーに悪印象を与えてアプリを削除されるリスクが高くなってきます。アプリを利用するユーザーは情報の新しさや質を重視する傾向があるので、同じ内容を複数回送信していたり、通知内容をカスタマイズしていなかったりすることも悪印象につながります。
サーバーの保守・運用に掛かるコストも考える
アプリを展開する規模によっては、サーバーの保守・運用に掛かるコストも考える必要があります。スマホアプリではオンラインサーバーに各種情報を保管し、ユーザーの端末がアクセスして情報を参照することが一般的です。したがって、アクティブユーザーが増えるほどサーバー管理に掛かるコストは高くなってきます。
アクセスが集中してサーバーがダウンするとアプリが利用できなくなり、ユーザーが離れる原因になります。広告活動やメディア展開などを実施した直後はサーバーを増設する対策が必要になるケースがあることは把握しておきましょう。
アプリ開発の全体像をまず網羅したいという方へのプレゼント!

「そもそもアプリ開発ってどうやって進めるの?」と疑問に思った方にぜひ読んでいただきたいのが、アプリ開発の流れを解説した無料eBook。
ちょっとしたスキマ時間で気軽に見れるボリュームなので、ぜひ一度ご覧になってみてください!
目的を明確にする
アプリを新規導入する際は、ユーザーにどういった情報や利益を提供するのか、目標とする収益額はどのくらいか、などの開発目的を最初に決めてからアプリ制作を始めるようにしましょう。例えば販促アプリを開発する場合、時期別の売上目標を立てておく必要があります。情報発信を目的とする場合は、ダウンロード数やアクティブ率を目安にすることが一般的です。
ただし、「とりあえず競合他社に勝つ」といった曖昧な設定ではなく、他社アプリのコンテンツ内容やアクティブユーザー数などを基に、自社アプリを導入する具体的な目標を決めることがポイントです。
数値的な目標とは別に、アプリを導入すること自体も検討が必要です。具体的な目的や知識を持たずにアプリを制作すると余分なコストが掛かりやすい傾向があります。また、リリース後の保守・運用を適切に実施しなければ新規ユーザーを確保することは難しく、支出だけが積み重なっていく状態になりかねないので注意が必要です。
継続的に収益を上げられるアプリを開発するには、売上やアクティブ率といったシンプルな目標を決めて、定期的に達成率を測定していく取り組みを実施していくことが大事です。
アプリ開発・運用の最新トレンド
ローコード/ノーコード開発の進化
2023年以降、ローコード/ノーコード開発プラットフォームの進化により、小売企業がアプリを開発・運用するためのハードルは大幅に下がっています。最新のアプリ構築CMSは、複雑な機能(位置情報サービス、多言語対応、複数の決済システム統合など)も専門的なプログラミング知識なしに実装できるようになりました。
特に重要なのは、OS更新時の対応コストが大幅に削減されている点です。プラットフォーム側がOS更新対応を一括して行うため、個別のアプリ開発者がその都度対応する必要がなくなっています。
また、マイクロサービスアーキテクチャやAPIベースの開発アプローチにより、既存のバックエンドシステム(在庫管理、CRM、POSシステムなど)とアプリを簡単に連携できるようになりました。これにより、アプリはビジネスの中核システムと緊密に統合され、単なるマーケティングツールから業務効率化・顧客体験向上のための包括的なプラットフォームへと進化しています。
まとめ
アプリはリリースして終了ではなく、ダウンロードした顧客が継続的にアプリを使ってくれるように保守・運用を実施する必要があります。特に重要なポイントとしては、コンテンツを定期的に更新したり、プッシュ通知を活用したりすることが挙げられます。
小売企業が提供するアプリの場合、キャンペーン情報や新製品の情報など、ユーザーの関心を引く情報を定期的に発信することで継続的な利用を促しやすくなります。連絡にプッシュ通知を用いて情報を確認しやすくする工夫も必要になってきます。
コンテンツ追加や機能アップデートを定期的に実施しやすくする方法として、アプリを自社開発する方法もあります。近年は優れたクラウド型のアプリ構築CMSが増えてきており、プログラミング知識がない人でもビジネス向けアプリを制作できる環境が整っています。
——————————————————–
アプリ構築CMSのなかでもおすすめなのが、スマートフォンアプリの開発実績が豊富な、弊社Yappliです。Yappliは、アプリの開発・運用・分析をクラウドからワンストップで提供するプラットフォームです。
プログラミングは不要。幅広いデザインの高品質なネイティブアプリを短期間で開発可能です。また、管理画面はブログ感覚で誰もが簡単に更新作業を行うことができます。そのため、専門的な知識は一切必要なく、非エンジニアでも運用可能です。
さらに、申請時のストアサポートや、リリース後のダウンロード施策など、アプリで成果を出すための運用支援もサポート。リリースから運用まで安心して任せることができるYappli。まずはお気軽に資料請求を!