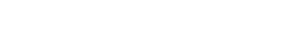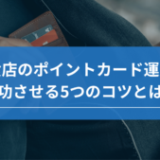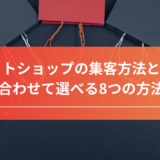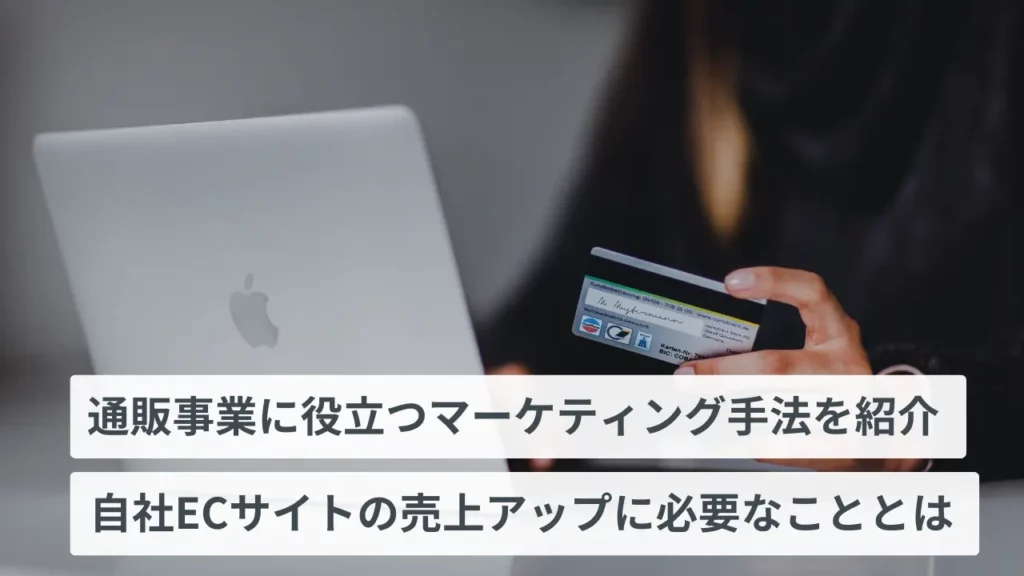
IT技術の進歩や消費者の購買行動の変化などの影響で、今まで実店舗を中心に販売してきたブランドの多くが、通販サイトも強化しようと試行錯誤しています。この記事では、運営中の通販サイトの売上をアップさせる施策に悩んでいる担当者や、これから自社通販サイトを立ち上げようとしている方に向けて、おすすめのマーケティング手法をご紹介します。
目次
通信販売(通販)とは
始めに通販に関する基本的なことからご紹介します。既に通販事業に取り組んでいる方もおさらいとしてご覧ください。
通販の定義
まずは通販とは何かを改めて確認しましょう。通販とは、何かしらの通信手段を使って売買が行われる販売方法で、例えばテレビショッピング番組では電話が、カタログでは郵便が、ネットショップではインターネットが使われているので、どれも通販に該当する販売方法となります。特に現代ではネットショッピングが主流になっており、売買されている商品ジャンルも本や雑貨をはじめ、食品や大型家電、旅行商品など多岐にわたっています。
通販なら実店舗を構える必要はなく、購買者と販売者が直接顔を合わせなくても売買できるので、店舗開発費や接客のための人件費がカットされ、立ち上げや運営にかかるコストが比較的かからないのが特徴。ユーザーにとっても、わざわざ店舗に足を運ばずとも、自分の好きなタイミングで商品を購入できるのでとても便利です。
通販には「総合通販」と「単品通販」がある
通販には「総合通販」と「単品通販」という2つの種類があります。それぞれ同じ通販ではありますが、特性もターゲット層も全く異なります。総合通販は「総合」という名が付いているように、様々な商品を総合的に取り扱うタイプの通販で、例えばAmazonや楽天市場が挙げられます。商品数が多く、幅広い顧客層を獲得できる反面、競合他社との個性を出しにくく、根強いファンを育てにくい傾向があります。
一方で単品通販は、1つの商品やカテゴリーに集中して商品を販売する販売手法です。最近では地方の名産品を手がけるメーカーも次々とネットショップを立ち上げていますが、それらのようなショップのほとんどが単品通販タイプになります。単品通販は総合通販よりも取り扱う商品数が少ないので、商品一つひとつの魅力を高めないと多くの集客は望めません。その分、商品ごとの個性がユーザーに伝わりやすくなるので、リピーターやファンは生まれやすいメリットがあります。このようにどちらも一長一短なので、特にこれから通販サイトを立ち上げようとしている方は、自社が置かれている状況を踏まえながらどちらのタイプにするのかを選びましょう。
通販事業は始めてすぐ効果が出るほど甘くない
日本通信販売協会がまとめた「2020年度(令和2年度)通信販売売上高について」によると、現在はコロナ禍の影響もあり、通販市場全体の売上は増加傾向にあります。また、市場は22年連続で拡大し続けており、インターネット・フリーダイヤル環境や輸送手段の整備、決済手段の選択肢の増加などが堅調な市場規模拡大に貢献しています。こういった背景から、これから通販事業に参入する価値は依然高く、消費者にとってネットショッピングは購買行動におけるスタンダードになっているので、自社でネットショップを持つことももはや当たり前となりつつあります。
実際、先述した地方の名産品を手がけるメーカーのように、日本全国で次々とネットショップが立ち上がっていますが、一方でオープンすればたちまち成功するほど甘くないのが現実です。ネットショップを開くのはいわばスタート。そこからどうやって集客し、売上に繋げていくのか、つまりマーケティング施策についてしっかりと詰めていかなければなりません。
販売促進の方法を検討する中で、近年注目度が高まっているのが「自社アプリ」の活用です。
本資料ではアプリを活用することで販売促進につなげる具体的な方法を、事例と併せて紹介しています。ちょっとしたスキマ時間で気軽に見れるボリュームなので、ぜひ一度ご覧になってみてください!
通販事業に役立つマーケティング手法
ここからは、通販事業の中でもインターネットを使った通販、つまりネットショップで売上を出すための効果的なマーケティング手法に絞って解説します。
マスマーケティング
いわゆる「4マス」と呼ばれるテレビ、新聞、ラジオ、雑誌を使ったマーケティング手法で、数あるマーケティング手法の中でも代表的な存在です。主に認知度アップが期待でき、特にテレビや新聞を活用した際の効果は絶大。後述する他のマーケティング施策を行う際も、マスマーケティングで認知を獲得していればより効果が生まれやすいので、検討する価値はあります。一方で、4マスを利用する際のコストは他のマーケティングに比べて高額になる可能性が高いので、どの企業でも気軽に実施できる手法ではないかもしれません。
ダイレクトマーケティング
マスマーケティングでは企業がユーザーにメッセージを届けるために、多くのユーザーが利用しているテレビやラジオをいわば「橋渡し役」として活用していました。一方でダイレクトマーケティングは、「橋渡し役」を介さず企業とユーザーが直接コミュニケーションする手法になります。この手法の重要なポイントは、ユーザーの属性を細かく分析し、ユーザーに価値あるものだと思ってもらえるような施策設計をしなければならないこと。4マスのように多くのユーザーが使っているものを介さないのであれば、ユーザーが普段接しているメディアや、必要としている情報は何かなどをしっかり把握しないと、ユーザーとコミュニケーションするどころか、そもそも出会うことさえままならないからです。
こう聞くとマスマーケティングの方が良いと思われるかもしれませんが、マスマーケティングは良くも悪くも不特定多数に届くので、ターゲットとなり得ない属性の人々にまでコストをかけて行き渡ってしまう側面があります。しかしダイレクトマーケティングは、狙った人々に絞って施策を実行していくためコストパフォーマンスに優れ、獲得したユーザーをリピーターやファンに育てやすいメリットも見逃せません。
なお、ダイレクトマーケティングはマスマーケティングよりもやや概念的な側面があり、後述するマーケティング手法も実施する内容によってはダイレクトマーケティングと捉えられるものもあります。
ウェブマーケティング
自社サイトやSNSなど、ウェブ媒体を中心に展開していくマーケティングのことで、ネットショップとの相性も高く、様々あるマーケティング手法の中でもまずはここから取り組むのがおすすめです。具体的な方法は、例えばYahooなどのポータルサイト上やGoogleなどの検索サイトの検索結果画面に広告を配置するようにしたり、人気のウェブメディアにてショップを紹介する記事広告を出稿するなどが挙げられます。
また、ネットショップの使いやすさをブラッシュアップすることも大切なウェブマーケティングの一つ。せっかく集客しても、そのページが見づらかったり、スムーズに会計できないなど、利便性が悪いと購入せず離脱してしまいます。ネットショップ担当ではないスタッフや友人、家族など、フラットな目線で評価できる人に改めてショップサイトを見てもらい、その感想を踏まえながら改善していくと良いでしょう。
【EC集客の成功事例】アプリ×CRMでLTVが135%アップ!
ネットショップ集客の成功事例として注目したいのが、アパレル企業チュチュアンナ様の取り組みです。
アプリを活用した顧客接点の強化により、アプリ経由のEC売上が全体の50%に到達。さらに会員のLTVが135%アップするなど、ECの集客で大きな成果を上げています。その戦略と実践方法を紹介しているので、ぜひご覧ください。
コンテンツマーケティング
ウェブマーケティングの説明時にご紹介したYahooやGoogleなどに配置する広告は、言い換えるとネットショップ側からユーザーに積極的に存在をアピールする手法です。一方でコンテンツマーケティングとは、ユーザーが求めているコンテンツを発信することで、ユーザー側から積極的に来訪するように設計します。例えば体重の増加が気になっている人がいたとして、その人は何も調べずにすぐ「A社の〇〇〇〇という商品を使って痩せたい」とは思わないでしょう。
まずは「どういうダイエット方法があるのだろう?」となり、その手段を調べるはずです。その際に「こういったダイエット方法がおすすめ」と紹介するのがコンテンツマーケティングの考え方。それがたとえ直接的に商品訴求になっていなくとも、まずはユーザーが求めている情報をネットショップやメールマガジン、SNSなどで発信し、ユーザーから関心を持って来訪してもらったのちに自社商品の訴求へと繋げます。
SEO
コンテンツマーケティングと合わせて取り組みたいのがSEO(Search Engine Optimization)。「Search Engine」、つまりGoogleなどの検索サイトへの最適化を図るという手法で、具体的にはユーザーがとあるキーワードで検索した際に、検索結果で自社のページを上位表示させようとする施策となります。ネットショップに限らず膨大な量のホームページが存在する中で、何の対策もなしにユーザーが検索サイトから自社のページまで辿り着くことは、よほど知名度がある企業やブランドでもない限り、まずあり得ません。
なので「ユーザーは普段どういった悩みや願望を持ち、どういう検索キーワードで調べるのだろう?」と検証し、そのワードで調べたユーザーに満足してもらえるようなコンテンツを用意し、上位表示させる取り組みが必要です。以前は該当するキーワードを多くコンテンツに盛り込むだけで上位表示される傾向がありましたが、検索サイトのシステムも向上した今では、コンテンツの内容そのものがユーザーにとって有益かどうかを自動で判別されるようになっています。そのため、SEOは単なるテクニック論ではなく、「ユーザーにとって価値ある情報とは何か?」を突き詰める取り組みと言えるでしょう。
インフルエンサーマーケティング
YouTuberやインスタグラマーなど、インターネット上で大きな存在感や影響力を持つ人々をインフルエンサーと呼び、彼・彼女たちの力を借りたマーケティング施策も注目を集めています。テレビ業界のような一般消費者の暮らしとはかけ離れた世界にいる有名人よりも、多くの人が気軽に利用しているYoutubeやInstagram上で活動しているインフルエンサーの方がより親しみやすく、発言に対する共感も得やすいことが特徴です。
2022年以降、InstagramやTikTokなどのSNSプラットフォームは単なる広告媒体から直接的な販売チャネルへと進化しています。「ショップ機能」の拡充により、ユーザーはアプリを離れることなく商品を発見から購入まで完結できるようになりました。
特に注目すべきはライブコマース(ライブストリーミング販売)の急成長です。中国市場で大きな成功を収めたこの手法は、日本でも2023年から本格的に普及し始め、リアルタイムでの商品紹介と即時購入の組み合わせが新たな販売手法として確立されつつあります。
あわせて読みたい!
1200人に聞いた、購買プロセスにおける アプリ・SNS・ウェブの使い分け調査
認知・検討・購買の各フェーズで最適な顧客接点について、1,200人に聞いたアンケート結果をもとにまとめています。DRM以外のマーケティングについても具体的なデータを知りたい方におすすめです。
AIを活用したパーソナライゼーション
2023年以降、生成AIの台頭により、通販サイトにおけるパーソナライゼーションは新たな段階に進化しています。従来の購買履歴に基づくレコメンドだけでなく、AIが顧客の好みや行動パターンを深層的に分析し、一人ひとりに最適化されたショッピング体験を提供することが可能になりました。
具体的な活用例として、AIチャットボットによる接客サポート、視覚的な商品検索(Visual Search)、バーチャルフィッティングルームなどがあります。これらのテクノロジーは、顧客の購買決定プロセスをスムーズにし、カート放棄率の低下にも貢献しています。
DRMの手法
ツーステップマーケティング
いきなり購入を促すのではなく、まずは商品のサンプル品を無料提供し、実際に利用して納得してもらってから購入へと導く手法をツーステップマーケティングと言います。サンプル品以外にも例えば化粧品なら「トライアルキット」や「トラベルキット」などと称して、通常サイズよりも少量版の製品を販売するのもこの手法と言えるでしょう。ユーザーにとってのデメリットもこれといってなく、ゆえにユーザーの満足度を高めやすい有効な手法ですが、サンプル品の用意やトライアルキットの開発などのコストがかかる点に注意。
メールマーケティング
いわゆる「メールマガジン」を活用するマーケティング手法。商品購入時に登録されたユーザーのメールアドレスに、おすすめ商品やセール案内などの有益な情報を定期的に配信することでリピート購入を促します。また、先ほどご紹介したツーステップマーケティングと組み合わせて、例えば「メールマガジンに登録してくれた方に商品のサンプルセットを無料でプレゼント」といったキャンペーンを実施すれば、購入まで至らずとも多くの見込み客のメールアドレスを効率的に取得することができるので、新規客の獲得にも活用できます。
メールマガジンは先述したダイレクトマーケティングの一つなので、ユーザーの属性を見極めて、適切な情報を届けないとすぐにマガジンを解約されてしまい、ブランドに対する印象も悪くなってしまいます。実行するにあたっては、自分が普段購読しているメールマガジンの内容を振り返るなどして、どういった内容が効果的かを深く検討するようにしましょう。
アプリマーケティング
スマートフォンのアプリを使ったマーケティング手法。今や老若男女関わらず多くの人々がスマートフォンを日常使いしているため、スマートフォンのアプリを軸にマーケティング施策に取り組もうとする企業はかなり増えています。アプリを通じて有益な情報を発信したり、ネットショップと連携させてアプリ上で商品を購入させることも可能です。
特に活用したいのが、ユーザーのスマートフォン画面上に届けたいコンテンツを表示させることができる「プッシュ通知」。先述したメールマーケティングの肝であるメールマガジンの開封率は約10%と言われる一方で、プッシュ通知の開封率は約30〜40%と非常に効果的です。近年はローコストで手早くアプリ開発ができるサービスも増えており、アプリを開発するハードルは下がっているため、検討する価値は大いにあるマーケティング手法です。
ネットショップでのアプリ活用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧になってみてください。
ボイスコマースとIoTの統合
Amazon EchoやGoogle Homeなどのスマートスピーカーの普及により、音声による商品検索や注文(ボイスコマース)が新たな購買チャネルとして成長しています。2024年現在、特に日用消耗品や食料品などのリピート購入において利用が増加しています。
また、スマート冷蔵庫やIoT家電との連携により、消費者の日常生活の中に自然に組み込まれた購買体験の提供が可能になっています。これらの技術を活用することで、顧客の購買障壁を下げ、リピート率の向上につなげることができます。
AR/VRショッピング体験
2024年現在、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)技術を活用した没入型ショッピング体験の提供が加速しています。特に家具・インテリア、ファッション、化粧品といった「試してから買いたい」商品カテゴリーでの活用が進んでいます。
ARを活用した「バーチャルトライオン」や実際の生活空間に商品を配置してみる「ルームビューア」機能は、オンラインショッピングの不確実性を減少させ、購入への自信を高める効果があります。これにより返品率の低下やカート放棄率の減少といった実務的なメリットもあります。
通販事業におけるマーケティング施策のTIPS
記事の最後に、通販事業におけるマーケティング施策を成功に導くための考え方についてご紹介します。
マーケティング手法は組み合わせて使うとより効果的
ここまでご紹介したマーケティング手法は一つだけを採用するよりも、複数を組み合わせてそれぞれ補完し合いながら施策を設計していくのがおすすめです。例えばインフルエンサーマーケティングで広く認知を獲得しながら、コンテンツマーケティングの考え方を用いて、ユーザーにとって有益なコンテンツをネットショップで発信して訪れた人々を着実に購買へと導くなど。現代はユーザーのライフスタイルや価値観も多様化しているので、マスマーケティングだけで一定の効果を得られたかつての時代よりも、マーケティングの難度は上がっています。
多種多様なユーザーたちにファンになってもらうために、様々な手法を組み合わせながら施策を実行し、その結果を踏まえてアップデートを積み重ねていきましょう。
ユーザーデータの分析が非常に重要
ネットショップは実店舗と比べてユーザーの購買行動を数値化しやすいのが特徴で、このデータを緻密に分析し、施策に昇華できるかどうかがマーケティング成功の鍵を握っていると言っても過言ではありません。例えばメールマーケティングとインフルエンサーマーケティングを実行した結果、メールマガジンからの集客数がSNSの集客数よりも多かったとしたら、より効果が期待できるメールマーケティングにかけるコストを増やす決断ができ、インフルエンサーを通じて発信した内容にズレはなかったかを振り返るきっかけにもなります。
つまり、数値を分析することで次なるアクションを実行しやすく、その精度も高められるので、マーケティング施策は決して実行しただけで満足してしまわないようにしましょう。なお、施策の質を高めるためにはその分多くのデータを分析しなければならないので、購買データなどを分析できるマーケティング支援ツールなどを活用するのが良いでしょう。
プライバシーファーストのデータ活用
2023年のGoogleによるサードパーティCookieの段階的廃止計画や、各国のデータ保護規制の強化に伴い、顧客データの収集・活用方法は大きく変化しています。ファーストパーティデータ(自社で直接収集したデータ)の重要性が高まる中、透明性の高いデータ収集と活用が求められています。
顧客との信頼関係を築きながらパーソナライズされた体験を提供するために、明確な同意取得プロセスの構築や、データの使用目的の明示など、プライバシーに配慮したマーケティング手法への移行が不可欠です。
サステナブルなECへの移行
2023年以降、消費者のサステナビリティへの関心はさらに高まっており、環境に配慮した商品選択や購買決定が増加しています。通販事業者においても、環境負荷の少ない包装材の使用、カーボンニュートラル配送オプションの提供、リサイクル・アップサイクル商品の取り扱いなど、サステナブルな取り組みが競争力の源泉となっています。
透明性の高い情報開示も重要なトレンドであり、商品の製造工程や原材料の調達方法、労働環境などの情報を積極的に公開することで、エシカル消費を重視する顧客層からの支持を集めることができます。
まとめ
通信販売の市場は堅調に拡大し続ける一方、競争も激化しています。また、通販サイトの売上向上に役立つマーケティング手法には様々な種類があり、長所も短所も異なります。自社の通販サイトでいずれかの手法を実践する際は、本記事で紹介した特徴を参考にしてください。
記事内でもご紹介しましたが、ネットショップの売上向上に効果を発揮するマーケティング手法の一つが、アプリの活用です。本メディアを運営する株式会社ヤプリは、ノーコード(プログラミング不要)のアプリプラットフォーム「Yappli」を提供しており、アプリの開発実績も数多くあります。記事をご覧いただいて、もしご自身が携わる通販事業でアプリを活用したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひヤプリにご相談ください。まずは資料請求から、お気軽にどうぞ。