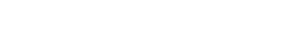ブランディングと聞くと、消費者などに対しての施策をイメージしがちです。しかし、自社のブランド価値や理念を浸透させる施策は、社内に向けても欠かせないものなのです。今回は、社内向けにブランド価値を浸透させる「インナーブランディング」について解説。目的やメリットをはじめ、インナーブランディングの具体的な事例や実践のポイントも併せて紹介しますので、ぜひブランディング戦略の参考にしてみてください。
製品やブランドのファン作りや売上創出にお悩みの方必見!
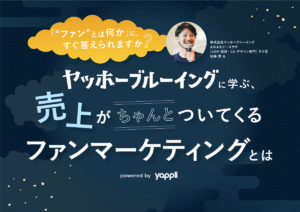 顧客一人ひとりのリピート購入・利用率を高めて安定的な収益を生み出しつつ、ファンとともに商品やサービスの向上をはかっていくとして、最近注目が高まっているファンマーケティング。成果の作り方が難しいファンマーケティングで売上を作る方法をヤッホーブルーイング様の事例をもとにご紹介します。
顧客一人ひとりのリピート購入・利用率を高めて安定的な収益を生み出しつつ、ファンとともに商品やサービスの向上をはかっていくとして、最近注目が高まっているファンマーケティング。成果の作り方が難しいファンマーケティングで売上を作る方法をヤッホーブルーイング様の事例をもとにご紹介します。
目次
- インナーブランディングとは?
- インナーブランディングのメリット
- インナーブランディングの注意点
- インナーブランディングの事例紹介
- 国内大手衛生用品メーカーの事例:ブランド価値を社内に浸透させた結果、消費者にも価値が届きやすくなった
- アメリカの大手オンラインシューズストアの事例:インナーブランディングによって社員の自主性が向上した
- 大手監査法人の事例:社会貢献の事例の共有が、社員のモラル向上とモチベーションアップにつながった
- 国内印刷企業の事例:日報と社内報を連動させ、社員と経営層の相互理解が深まった
- 国内インターネット広告事業会社の事例:合宿を通じて社員が役員の考えや視点を共有し、売上増につながった
- 国内航空会社の事例:サンクスカードの導入により、部門間の相互理解と社内の一体感が向上した
- 冷凍食品メーカーの事例:独自のキャッチフレーズが社内に浸透した結果、働き方の理想像が共有された
- 高級ホテルの事例:現場の社員に経費の支出内容を決定できる権限を与え、サービスの質向上につなげた
- インナーブランディング実践のポイント
- インナーブランディングの具体的手法
- まとめ:自社アプリを活用してインナーブランディングに寄与する選択肢もある
インナーブランディングとは?
インナーブランディングとは、自社の企業理念やブランド価値を「自社の社員向けに」浸透させる活動の総称です。まずは、インナーブランディングの定義や目的のほか、重要な理由について整理しておきましょう。
インナーブランディングの別称
インナーブランディングには、実はさまざまな呼び方があります。よく使われている呼称は下記のとおりです。
- インターナルブランディング
- インナーマーケティング
- インターナルマーケティング
呼称はそれぞれ異なりますが、いずれもインナーブランディングと同じ意味で用いられます。それぞれ概念が異なるわけではないという点に注意してください。
インナーブランディングの目的
自社の企業理念やブランド価値を社員が正確に理解し、共有できるようにすることがインナーブランディングの主な目的です。部門や担当者によって自社ブランドに対する解釈に差異が生じるのを防ぎ、一貫性を図ることが狙いといえます。
インナーブランディングが重要な理由
インナーブランディングが徹底されていない場合、自社のブランド価値を社員が個人的な解釈にもとづいて判断することになります。そうなると、部門や担当者によって解釈がまちまちになり、消費者に向けて発信するブランドの価値や理念が揺らいでしまうおそれがあるでしょう。
インナーブランディングは社員一人ひとりが自社ブランドを自分事として捉え、ブランドの価値を深く理解し、社内の共通理解にもとづいて行動するために必要な施策といえます。ブランド価値が社内に浸透すると、より精度の高い統一感のあるブランド価値を消費者に提供できるのです。
エクスターナルブランディングとの違い
消費者やユーザーなど、社外の対象者に向けて行う商品のブランディング施策は「エクスターナルブランディング」と呼ばれます。インナーブランディングは社内向け、エクスターナルブランディングは社外向けと考えるといいでしょう。単に「ブランディング」という場合、多くのケースではエクスターナルブランディングを指しています。社外向けのブランディング戦略と区別するために、あえてインナーブランディングと呼んで区別しているのです。
ブランディングについてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
インナーブランディングのメリット
インナーブランディングに取り組むことで、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。主なインナーブランディングのメリットとして、大きく下記の3点が挙げられます。
社員のブランド理解が促され、組織のパフォーマンスが向上する
自社ブランドに対する社員の理解が深まり、組織全体のパフォーマンス向上につながることが、まず挙げられるインナーブランディングのメリットです。自社に対するイメージが明確になることで、社員はより深く正確にブランド価値を理解した行動をとれるようになります。社員が自社ブランドを正しく理解していなかったり、自社ブランドへの評価が低い状態で業務にあたっていたりすると、消費者にもブランド価値が伝わりづらく、伝わったとしても間違った価値として捉えられてしまうかもしれません。ブランドの理念や価値が高いレベルで共有されれば、社員が自社の魅力を正しく発信できるようになります。つまり、インナーブランディングの強化はエクスターナルブランディングの強化にもつながり、ブランド価値の向上に寄与します。
社員一人ひとりのロイヤリティが上がり、社員同士の連帯感が強化される
ブランド価値が社内に浸透すると、自社に対する社員のロイヤリティ(忠誠心)やエンゲージメント(愛着)が高まります。結果として自社に対する信頼感が増し、より貢献したいと感じる社員を増やすことができるはずです。また、ブランド価値の浸透は、社員間の共通理解を強化します。同じ目標に向かって仕事に取り組みやすくなり、社内の連帯感が高まることもインナーブランディングのメリット。現場での業務目標に対する説明の時間が省かれ、部門間や担当者間でのコミュニケーションコストが抑制されることで、より働きやすい環境の構築に役立ちます。
社員の定着率向上、共感する人材の採用につながる
自社ブランドへの愛着が高まると、より長く貢献したいと考える社員が増えることが予想されます。そうなると、社員の定着率が向上し、新規採用のコスト抑制にもつながるはずです。また、人材を採用する際にも、インナーブランディングが浸透していると、ブランド理念に共感する人材を見極めやすくなります。ブランド理念への理解度が高い人材を採用できれば、入社後の教育に要する時間やコストを抑えることもできるでしょう。
インナーブランディングの注意点
インナーブランディングには数多くのメリットがある一方で、注意しておきたい面もあります。インナーブランディングは、どういった点に気をつけるべきか、その内容についてご紹介します。
コストがかかる
インナーブランディングを推進するには、社員への情報発信や情報共有するための仕組みづくりが欠かせません。そのため、社内向けの施策とはいえ、人件費などのコストがかかる点には注意が必要です。また、エクスターナルブランディングとは異なり、売上や収益への直接的なつながりが見えづらい点に要注意。コストをかける意義を明確にしておかないと、何のために取り組んでいるのか、どうすれば成功で、どのタイミングで見直しが必要なのかもわからなくなり、結果的にプロジェクトが中途半端なところで頓挫してしまう可能性があるので気をつけましょう。
中長期的に考える必要がある
社内にブランド理念や価値を浸透させるには、一定の期間が必要です。インナーブランディングに取り組んでも即座に効果が表れるわけではないため、中長期的な計画に則って粘り強く継続する体力が求められます。プロジェクトが中だるみしないよう、施策の目的やゴールを関係者間で共有し、定期的に達成度を確認するプロセスが不可欠となるでしょう。
価値観の押し付けはNG
インナーブランディングは社員にブランド価値を浸透させるための施策とはいえ、企業が理想とする価値観を社員に押し付けないよう注意する必要があります。本当の意味でブランド価値を浸透させるためには「共感」がなくてはなりません。ブランド価値を絶対的なルールとして扱うのではなく、社員一人ひとりの考えや意見なども尊重し、共感してもらえるところから無理なく浸透させていく姿勢が大切です。
バリューが不十分の場合、逆効果にもなりうる
ブランド価値そのものが十分に考え抜かれ、明確なバリューを打ち出したものになっていないと、インナーブランディングはかえって逆効果にもなりかねません。バリューが不十分であることが社員に浸透してしまい、むしろ不信感につながるおそれがあるからです。ブランドの理念・価値にバリューがあることは、インナーブランディングに取り組む上で前提条件になると考えてください。
インナーブランディングの事例紹介
ここからは、インナーブランディングの具体的な成功事例を紹介します。インナーブランディングが社内の一体感を高め、結果的にエクスターナルブランディングにも寄与するイメージをぜひつかんでください。
国内大手衛生用品メーカーの事例:ブランド価値を社内に浸透させた結果、消費者にも価値が届きやすくなった
国内大手衛生用品メーカーでは、自社の存在意義やアイデンティティの浸透に取り組みました。広報部門はもちろんのこと、経営トップみずからが企業メッセージを社内に発信し、ブランド価値を浸透させたのです。一連の取り組みは商品開発に反映されただけでなく、社員の日常的な行動レベルにも好影響を与え、ブランド価値が消費者により届きやすくなりました。
アメリカの大手オンラインシューズストアの事例:インナーブランディングによって社員の自主性が向上した
アメリカの大手オンラインシューズストアでは、自社のクレド(社員が心掛けるべき信条や行動指針)をコアバリューとして掲げています。同社は、社員に大きな裁量を与えることでも知られており、業務内で判断に迷いが生じた際には、クレドに立ち返れば良いという共通理解が醸成されました。インナーブランディングが社員の自主性向上に役立った好例といえます。
大手監査法人の事例:社会貢献の事例の共有が、社員のモラル向上とモチベーションアップにつながった
グローバルに展開している大手監査法人では、社員の仕事が社会に貢献した事例をインタビュー動画として収集し、社内の誰もが見られるイントラネットに公開しました。社員は、自身の仕事が科学技術の向上や世界平和の実現に貢献していることを再認識することができたようです。一連の取り組みは社員のモラル向上とモチベーションアップに寄与しました。
国内印刷企業の事例:日報と社内報を連動させ、社員と経営層の相互理解が深まった
国内のとある印刷企業では、日報と社内報を連動したインナーブランディングを促進する取り組みをしています。社員の日報に経営者や管理職がコメントをし、社内報に掲載するという内容です。これにより、社員と経営者・管理職の相互理解が深まり、「共に組織を作っていく」という文化が築かれています。
国内インターネット広告事業会社の事例:合宿を通じて社員が役員の考えや視点を共有し、売上増につながった
国内インターネット広告事業会社では、役員と社員がチームを組み、新規事業提案や課題解決のための提案を徹底的に話し合う合宿を実施しています。合宿を通じて社員は役員の考えや視点を共有し、自社の状況をより深く理解することができるのです。合宿を通じて生まれたアイディアによる売上は、累計700億円にも上るそうです。
国内航空会社の事例:サンクスカードの導入により、部門間の相互理解と社内の一体感が向上した
国内航空会社では「サンクスカード」を取り入れ、社員がお互いに感謝を伝え合えるようにしています。サンクスカードに記載する内容にルールは設けず、自然に活用しやすい形にしたことがポイント。サンクスカードのやりとりを通じて部門間の相互理解が向上し、社内の一体感が高まったようです。
冷凍食品メーカーの事例:独自のキャッチフレーズが社内に浸透した結果、働き方の理想像が共有された
国内冷凍食品メーカーでは、社内活性化プロジェクトとして「とらわれず、明るく」という思いを込めたキャッチフレーズを掲げました。キャッチフレーズが社内に浸透することで、自社が掲げている働き方の理想像が社員間で共有されるようになったようです。これは、社内共通語を醸成することで、理念の浸透に成功した事例といえます。
高級ホテルの事例:現場の社員に経費の支出内容を決定できる権限を与え、サービスの質向上につなげた
グローバルに展開する高級ホテルグループでは、宿泊客に「最高の瞬間を提供する」ために社員が自分の判断で行動することを推奨しています。ユニークなのは、現場の社員が一定額の経費の支出内容を決定できる権限が与えられていることです。この権限は、宿泊客が求めるサービスを社員一人ひとりが考え抜き、サービスの質を向上させることに寄与しました。業務を与えられたものとしてこなすのではなく、自分事として捉えてもらうことに成功した事例といえます。
インナーブランディング実践のポイント
続いては、インナーブランディングを実践し、社内にブランド価値を浸透させるためのポイントを紹介しましょう。ポイントを押さえて実践することで、より効果的にインナーブランディングを実現できるはずです。
会社・製品の確固たるビジョンを定める
インナーブランディングでまず取り組むべきは、会社・製品のビジョンを明確にすることです。これはブランド価値の原点となるため、急に変更したり解釈を変えたりするのは好ましくありません。自社や自社製品の存在意義に立ち返り、自分たちは何のために存在しているのかを深掘りしましょう。
ビジョンステートメントを用意する
ブランドの理念は、ビジョンステートメントとして明文化しておくことが大切です。コアバリューやミッションなどを掲げることで、社員は自社のブランド価値をより認識しやすくなります。ブランドとして実現したい世界観や価値観をできるだけ詳細に記載し、社員間の共通認識としていくのがポイントです。
評価・フィードバックを実施する
ビジョンステートメントは社員に告知・配布するだけなく、定期的に理解・共有の度合いを評価していく必要があります。単に認知度が高まっているかどうかだけでなく、ビジョンステートメントが社員のモラル向上やモチベーションアップに寄与しているかを確認することが大切です。
教育・トレーニングを定期的に行う
自社のブランド理念や価値への理解を促すために、社員への教育や理解を深めるトレーニングの機会も定期的に設けましょう。新入社員研修などで一度実施しただけで終了するのではなく、継続的に教育の機会を設けることが重要です。担当業務の根幹にブランド理念があることを定期的に確認することにより、社員はブランド価値を自分事として捉えることができます。トレーニングは入社年数や役職などに応じた内容にし、参加する社員が当事者意識を持って参加できるように工夫することも大切なポイントです。
インナーブランディングの具体的手法
インナーブランディングには、決まった手法があるわけではありません。社員にブランド理念・価値を浸透させるという目的さえ達成できるのであれば、どのような手法をとっても問題ないのです。一例として、下記にインナーブランディングの推進に役立つ具体的な手法を紹介します。
社内報
自社のビジョンやミッション、バリューを定期的に周知し、社員に再認識してもらう上で有効なツールが社内報です。従来は紙ベースの冊子を配布する方法が一般的でしたが、近年は社内報をイントラネットなどに掲載する企業も増えています。ブランドメッセージを毎号必ず掲載するほか、ブランド理念が実践で活かされた事例を紹介するといった工夫を加えると、より効果的です。
クレド
すべての社員にとって行動規範となるクレドを掲げることも、インナーブランディングの代表的な手法です。部門や担当業務・ポジションの違いによらず、あらゆる社員の判断基準となるクレドを掲げることで、組織の一体感が強化されます。クレドを掲げるだけでなく、経営陣や管理職がクレドを引き合いに出してメッセージを発信することで、社内への浸透がいっそう促進されるはずです。
社内イベント
実務以外に社員同士が交流できる社内イベントを実施すれば、関係性の強化や社員同士の相互理解を深める効果があります。社員たちが業務から離れて交流することで、互いの新たな一面を知ることができるからです。ただし、社内イベントの目的がブランド理念への理解促進であることを忘れないようにしなくてはなりません。社員が義務的に参加することのないよう、イベントの目的を周知することも大切です。
ワークショップ
ワークショップ形式の研修を実施することも、自社ブランドの理解を深めることに役立ちます。より実務に即した内容にすることで、社員に実践してほしい行動を体験してもらうことができるからです。座学研修と比べて社員が当事者意識を持ちやすく、自身がブランド価値を担う一員であることへの自覚を促せるでしょう。
マネジメント・カンファレンス
経営陣と社員が合同で意思決定をしていく、対話形式の会合がマネジメント・カンファレンスです。経営陣の考えや方針を社員が直接聞けるだけでなく、社員が意見を直接伝えられるというメリットがあります。経営陣と社員が対話を通じて相互理解を深めることで、自社のブランド理念をより正確に共有できるのが特徴です。
日報
単なる業務の記録として捉えられがちな日報も、活用の仕方によってはインナーブランディングの推進に役立ちます。日報は、上司が部下の思考を知るきっかけとなり得ます。部下の思考を知れば、彼らがブランド理念に則って行動できているかを判断することもできるでしょう。上司が日報にコメントをすれば、ブランド理念にもとづく考え方や行動を浸透させていく上でも役立ちます。
サンクスカード
サンクスカードは、社員同士が感謝の気持ちを伝え合う手法です。日常業務でのちょっとした気遣いや配慮に対して感謝を伝え合うことで、社員間の信頼関係を高める効果が期待できます。また、ポジティブな言葉を伝え合う行為そのものが企業文化となり、ブランド理念共有の土壌を作る上でも有効です。
社内SNS
社内SNSは、部門を超えた意思疎通に役立ちます。メールやビジネスチャットは用途が業務連絡に特化されがちですが、社内SNSであれば業務以外の話題も上がりやすいでしょう。他部署の取り組みや他部門の管理職の考え方を知る機会にもなるため、ブランド理念の共有を強化することに役立ちます。
トップメッセージ
経営トップが、自社ブランドに関するメッセージを発信することも忘れてはなりません。トップみずから社員に語りかけることにより、部門ごとの方針ではなく全社の方向性として社員に周知できることがメリットです。会合などの場で社長が発言する以外にも、動画メッセージをイントラネットに掲載したり、社内報にトップメッセージを掲載したりする方法があります。
1on1
1on1は、上司と部下が1対1で話せる場を設け、各自の課題や困っていることを上司と共有する手法です。上司が解決策を示す際は、常にブランド理念に立ち返って判断していることを継続的に部下へ伝えていきましょう。部下はブランド理念を自分事として捉えやすくなり、将来的には自分の部下に対して同様の指導をするようになるはずです。
トップキャラバン
トップキャラバンは経営陣が現場を訪問し、社員と直接対話をする機会を設ける方法です。現場の視察や内部監査ではなく、社員との「対話」が目的であることが大きなポイントといえます。経営陣がみずからブランド理念を語り、社員との対話を通じて理解を深めていくことにより、ブランド理念が現場に浸透しやすくなるはずです。
エバンジェリスト育成
ブランド戦略の責任者として、自社のブランド理念を発信・浸透させていく役割を担う人材をエバンジェリストといいます。エバンジェリストは商品開発やマーケティング、広報といった部門をまたいでブランド理念を発信し、組織の隅々までブランド理念が浸透することを目指します。エバンジェリストを複数育成していくことで、社内にブランド理念が浸透する速度や度合いを高めることができるでしょう。
まとめ:自社アプリを活用してインナーブランディングに寄与する選択肢もある
インナーブランディングは、自社ブランドの価値や理念を社内に浸透させるための施策全般を表す概念です。インナーブランディングを強化することによって、社員は自社ブランドの理念や価値を共有し、理解を深めることができます。さらに、社員が自社ブランドをより正確に消費者へ届けられるようになり、エクスターナルブランディングの精度が高まることが期待できます。
インナーブランディングを高めていくには、自社アプリを活用するという手もあります。その際には、本メディアを運営する株式会社ヤプリが提供する、プログラミング不要のノーコードで自社アプリを作成できるアプリプラットフォーム「Yappli」を試してみてはいかがでしょうか。自社アプリは社員のスマートフォンで閲覧することもできるため、ブランド理念を周知する機会を増やす上でも有効です。今回紹介したインナーブランディングの施策を実践する際には、ぜひYappliの活用をご検討ください。
>>こちらの記事もおすすめです