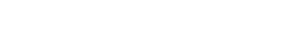従業員のワークエンゲージメントを高めることは、なぜ企業にとって重要なのでしょうか。
本記事では、ワークエンゲージメントの定義や測定方法に加え、ワークエンゲージメントを向上させるための方法や、それが企業にもたらすメリットについて解説しています。従業員や組織のパフォーマンスを向上させる方法を探している方はぜひ参考にしてください。
企業と従業員のエンゲージメントを作るためのGuide Book!

働き方や仕事における価値観が変化している昨今において、従業員が自身の日々の仕事に満足できるような体験を提供することで、組織エンゲージメントを高める方法について丁寧に解説。組織エンゲージメントの向上はなぜ近年、そして今後より大切になっていくのかや、アプリなどのデジタルツールを活用して、従業員の業務を効果的にサポートする方法などを紹介します。
ワークエンゲージメントとは?
ワークエンゲージメントとは、従業員の精神状態が仕事に対してポジティブである状態を意味しています。言い換えれば、従業員が熱意や集中力、主体性を持って前向きに仕事へ取り組めているかを表す指標です。ワークエンゲージメントが高い従業員は、強い熱意や責任感を持って業務を遂行しており、労働生産性の向上や職場の雰囲気を改善してくれると期待できます。
ワークエンゲージメントの特徴は、一時的な感情を指すものではないことです。その日の気分や出来事で、仕事に取り組む姿勢が変わってしまうのは珍しいことではありません。「あの顧客は苦手」「この仕事は好き」といったように、特定の対象に対する好き嫌いが出ることもあります。
ワークエンゲージメントはそうした一時的な気分や特定の対象に向けた感情ではなく、仕事全体に対する持続的で全般的な感情を指しています。
目次
ワークエンゲージメントの3つの要素
2019年に厚生労働省が公表した資料によれば、ワークエンゲージメントは「活力」「熱意」「没頭」の3要素で構成され、これらがすべて揃った状態だと定義されています。
参考:「働きがい」をもって働くことのできる環境の実現に向けて|厚生労働省
活力
活力とは、仕事に対する前向きなエネルギーや心理的な回復力のことを指しています。つまり、活力があるとは、仕事に対する情熱を強く持ち、努力を惜しまず、ストレスを受けるような状況が発生しても、やる気が損なわれない状態です。
仕事へ専心して取り組むために必要な精神的スタミナを持っていると言い換えることもできます。強い活力がある従業員は、業務上で逆境や困難に直面しても、自分の力で乗り越えようという姿勢で臨みます。
熱意
熱意とは、仕事に対して強い関心や誇り、積極的な価値を見出している精神状態のことを指します。
仕事に対して熱意を持つ従業員は、担当している業務の内容に深い関心を持ち、誰に指示されずとも主体的に仕事に取り組みます。業務を遂行する上で役立つ知識やスキルを習得し、新しいサービスや業務改善方法の提案なども積極的に行います。
没頭
没頭とは、仕事への集中力や没入感を表し、時間が経つのを忘れてしまうほど仕事に夢中になっている状態のことを指します。仕事に没頭している従業員は、高い作業効率で仕事をこなし、成果物の品質も高い傾向にあります。場合によっては、業務時間が終わっても気分を切り替えることができず、仕事のことが頭から離れないようなこともあります。
ワークエンゲージメントに関連する概念
従業員の仕事に対する精神状態を表す概念には、ワークエンゲージメントのほかにもバーンアウトやワーカホリズム、職務満足感があります。
バーンアウト
バーンアウトとは、仕事に過度のエネルギーを投じたことが原因で生じる心身の疲労感や無気力状態のことです。日本では「燃え尽き症候群」と呼ばれることもあります。投じたエネルギーに比べて、得られた結果が見合わない場合などにバーンアウトが起こる可能性があります。仕事に対する前向きな意欲が喪失されてしまっており、ワークエンゲージメントとは対極にある状態だといえます。
ワーカホリズム
ワーカホリズムとは、仕事をしなければいけないという強い強迫観念から、過度に仕事を行ってしまう状態のことを指します。業務を積極的にこなしている状態は、表面的にはワークエンゲージメントと変わるところはありません。ただし、ワークエンゲージメントでは、従業員本人が深い充実感や肯定感を持ちながら仕事を行っているのに対し、ワーカホリズムの場合は「ミスがないか気になって仕事のチェックをやめられない」など、不安感や焦燥感といった否定的な感情に突き動かされている点に大きな違いがあります。
仕事に没頭するという点では同じでも、ワーカホリズムとワークエンゲージメントとでは、仕事に対する精神状態は180度異なります。
職務満足感
ワークエンゲージメントと混同されやすいのが職務満足感です。職務満足感とは、自分の仕事を客観的に評価した場合、ポジティブに捉えている精神状態のことを指します。仕事に満足しているという点ではワークエンゲージメントと同じです。
ただし、職務満足感が「客観的な評価」にもとづくのに対し、ワークエンゲージメントでは「没頭」という主観的な要素が重要になってきます。職務満足感は仕事を後から振り返った時には充実していても、熱意的に仕事に没頭しているわけではないので、ワークエンゲージメントよりも活動水準が低いといえます。
ワークエンゲージメントが注目される背景
ワークエンゲージメントが注目される背景には、労働市場における慢性的な人材不足や人材の流動化、働き方の多様化といった状況があります。現代の日本では少子高齢化によって労働人口の減少が進んでおり、多くの業種・職種で慢性的・構造的な人材不足に陥っています。企業間での人材獲得競争が激化し、優秀な人材を確保することは年々難しくなっている状態です。
ワークエンゲージメントの向上は離職率の低下に直結するだけでなく、ワークエンゲージメントを向上させようとする企業の取り組みが、就職先に働きがいを求める求職者に対して好印象となる可能性があります。
さらに近年、長らく日本特有の雇用慣行であった終身雇用制度が崩壊しつつあり、人材の流動性が高まっていることも、ワークエンゲージメントに大きく関係します。現在は、キャリアアップのために転職する人は珍しくありません。こうした状況で優秀な従業員を自社に定着させ、高いパフォーマンスを発揮し続けてもらうためには、ワークエンゲージメントを高めることが重要です。
ワークエンゲージメントの高い従業員は仕事に対する意欲が強く、満足度も高いため、流出してしまうリスクは低くなります。
社会全体の働き方が変化してきていることも、ワークエンゲージメントが注目される要因のひとつです。2019年から順次施行が開始されている働き方改革関連法や、2020年から発生したコロナ禍を契機に導入が進んだテレワークやフレックスタイムにより、昨今は働き方が多様化しています。
さらには副業などを許可する企業も急激に増え、求職者がライフスタイルに合った働き方を選ぶことができるようになりました。
その一方で、企業と従業員の精神的な結びつきが弱くなり、仕事に対する従業員の積極性の欠如やパフォーマンスの低下などが問題になってきています。コロナ禍では働き方の変化に適応できず、メンタルヘルスの不調に陥る労働者も増加しました。 こうした状況を踏まえ、従業員のパフォーマンスを最大化したり、従業員の心身の健康をサポートしたりするために、ワークエンゲージメントの向上に取り組む企業が増えてきています。
ワークエンゲージメントの測定方法
自社のワークエンゲージメントの測定方法には、ワークエンゲージメントを直接計測する方法と、対極にあるバーンアウトを計測することにより、間接的にワークエンゲージメントを計測する方法があります。
UWES
UWESは”Utrecht Work Engagement Scale”の略であり、ワークエンゲージメントを直接、測定する方法です。ワークエンゲージメントを構成する活力・没頭・熱意の3つの要素に対して計17の設問で評価を行います。
バーンアウトの度合いを測定するMBI-GS やOLBIとは対照的に、仕事に対するポジティブな感情や認識、行動を評価します。UWESのスコアが高いほど、対象者が高いワークエンゲージメントを持っていると判断できます。比較的安定性が高い測定方法であり、日本で最も多く利用されている手法です。
MBI-GS
MBI-GSは”Maslach Burnout Inventory – General Survey”の略で、バーンアウトの度合いを測定するための評価テストです。MBI-GSでは「疲労感」「冷笑的態度(シニシズム)」「職務効力感」の3つの観点から対象者のバーンアウトの進行状態を評価します。疲労感は心身の消耗度、冷笑的態度は仕事や同僚に対する共感や関心の欠如、職務効力感は自分や自分の仕事の価値への否定感のことです。
MBI-GSは、バーンアウトの早期発見や予防対策を通して、間接的にワークエンゲージメントの向上に取り組める手法です。
OLBI
OLBIは”Oldenburg Burnout Inventory”の略で、MBI-GSと同様、バーンアウトの度合いを測定するための評価テストのひとつです。「疲弊」「離脱」の2つの観点から対象者の精神状態を評価し、バーンアウトの進行度を測定します。
疲弊とは心身の消耗度、離脱とは仕事に対する心理的な距離の遠さのことであり、仕事への共感や関心がどの程度低下しているかが明らかになります。MBI-GSと同様、OLBIのスコアが低いほどワークエンゲージメントが高いと判断されます。
ワークエンゲージメントを高めるメリット
ワークエンゲージメントを高めることは、従業員の心身の健康維持・増進に寄与するだけでなく、企業活動にもメリットがあります。
生産性の向上
厚生労働省の資料によれば、人手不足であるか否かを問わず、ワークエンゲージメントスコアの高い企業ほど、「個人の労働生産性が3年前と比較して向上していると感じる」割合が高いことがわかります。 高いワークエンゲージメントを持つ従業員は、業務で役立つ新しい知識やスキルを習得することに前向きです。
職場単位でワークエンゲージメントを見た場合には、スコアの高い職場では従業員が強い連帯感を持ち、会議などでも新しいアイデアや改善案などを活発に出してきます。従業員によるこうした動きは、生産性を向上させる上で重要です。
参考:第2-(3)-11図 ワーク・エンゲイジメントと個人の労働生産性について|令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-|厚生労働省
顧客満足度の向上
ワークエンゲージメントが高い従業員は、顧客に好印象を与えます。
こうした従業員は自らの役割を深く理解しており、自身の仕事がどのような価値をもたらすのかを把握していると顧客に伝わるからです。
ワークエンゲージメントの高い従業員は顧客の問題を解決するために積極的に動き、顧客に信頼感や安心感を与えます。信頼感や安心感は顧客満足度を高めるための重要な要素であり、顧客満足度の向上はリピーターの獲得やLTV(顧客生涯価値:Life Time Value)の向上などにもつながり、企業の収益を向上させます。
メンタルヘルス対策
ワークエンゲージメントを向上させることは、近年注目されているメンタルヘルス対策にもつながります。
強いストレスを抱えた従業員は仕事に集中できず、パフォーマンスが低下したり、ミスを頻発したりといったことによって、業績に悪影響を及ぼす可能性が高いといえます。メンタルヘルスの不調が長引けば、欠勤や休職・退職などにもつながり、組織としての安定性を欠くことになります。
ワークエンゲージメントが高い職場を作るためには、従業員が強い活力やストレス耐性を持ち、心身の健康状態を維持・増進することが大切です。ワークエンゲージメントを向上させる取り組みでは、必然的に従業員のメンタルヘルスも配慮することになります。
離職率の低下
ワークエンゲージメントの向上は、離職率低下に直結します。ワークエンゲージメントの高い従業員はストレスに高い耐性を持っているので、離職したいという意思が芽生えにくくなります。 厚生労働省の資料でも、ワークエンゲージメントと定着率や離職率は相関関係にあることがうかがえると述べられています。
参考:労働経済の分析|厚生労働省
ワークエンゲージメントを高める要因
ワークエンゲージメントを向上させる要因には「仕事の資源」「個人の資源」の2つがあり、この両方を最大化させるための取り組みが必要です。
仕事の資源
仕事の資源とは、職務の性質や量、職場環境、組織文化など、企業が主体的に調整できる要因です。
仕事の資源が大きくなるほど、従業員のストレスは軽減され、仕事に対する意欲や満足感が高まることが期待できます。
例えば、業務に関する上司や同僚からのサポートも仕事の資源のひとつです。具体的には、上司が従業員の達成目標に対してフィードバックをしたり、同僚間で情報を共有したり、協働関係を強化したりといったことが挙げられます。
これにより従業員は自身の業務を効率的に遂行でき、困難に直面した時も適切な対応を取れるようになります。
従業員に対してトレーニングの機会を提供することも重要です。新しいスキルを習得したり、すでに身についているスキルをさらに強化したりすることによって、従業員は自己成長を感じることができ、ワークエンゲージメントを高めることにつながります。もちろん、個々の従業員が快適に働ける職場環境を整えることも欠かせません。
個人の資源
仕事の資源が、企業が従業員に提供する外的要因であるのに対し、個人の資源は従業員自身の内的要因です。
例えば、個人の資源のひとつに自己効力感があります。自己効力感とは、物事へ適切に対処し、「自分には仕事を達成する能力がある」と信じられている状態を指し、ワークエンゲージメントとの相関が特に高いことが知られています。
自己効力感は、自分自身の成功体験や、他人の成功を観察した経験、自分に能力があることの言葉による説明、高揚感、成功を想像する力の5つが要因であり、これらを高めることが自己効力感を向上させ、個人資源の充実につながります。
個人の資源は内的要因ではあるものの、周囲からの働きかけによって豊かにすることもできます。例えば、従業員の努力や成果に対して、上司や同僚が積極的に称賛してくれるような環境では、自己効力感は高まりやすくなります。 個人の資源を充実させることは、従業員が自分の力を信じ、根気強さやチャレンジ精神を持って業務に従事するために重要です。ワークエンゲージメントを向上させるには、仕事の資源で示した外的な要因への働きかけ以外にも、個人の資源である従業員の内的要因に配慮することが欠かせません。
ワークエンゲージメントを高める上でのポイント
ワークエンゲージメントを向上させるためには、企業側にはおもに仕事の資源を、従業員側にはおもに個人の資源を充実させるための取り組みが求められます。具体的には、思いやり行動や仕事を進めやすい環境の整備、ツールの利用といったことが挙げられます。
思いやり行動をする
思いやり行動とは、従業員同士が互いに気遣いや助け合いの精神を持って行動することです。
具体的には、多くの仕事や困難な仕事を抱えている同僚を自発的にサポートすることなどが挙げられます。もちろん、単に「思いやりを持とう」と呼びかけるだけでは効果は期待できません。困っている同僚を助けたいと思っても、その方法がわからなかったり、見当違いなことをしてしまったりする人もいます。
思いやり行動を適切に実践するためには、まずは従業員同士で話し合い、具体的にどのような行動が困っている人の助けになるのかを明確にすることが重要です。
その後、話し合いのなかで提案された行動を職場で実践します。実践を開始したら、例えば2週間後などに効果や改善策について再度話し合う機会を作ることも必要です。ワークエンゲージメントを向上させるには、思いやり行動と改善とを継続し、職場のコミュニケーションや結束力を高めることが重要です。
環境整備をする
ワークエンゲージメントを向上させるには、物・心両面で働きやすい環境を整備することも重要です。
物理的な面では、多くの人が気軽に交流しあえる開放的なオフィス環境作りや、一人で集中したい時に使える個別ブースの設置などが挙げられます。社内カフェの設置など、リラックスできる環境を整えることも効果的です。
精神的な面では、従業員が自分の意見を安心して述べられるオープンな企業風土の醸成や、公平公正で透明性の高い人事評価制度の整備などが挙げられます。こうした環境の整備によって従業員は心理的安全性が得られ、積極的な気持ちで仕事に向かえるようになります。
さらに、特定の従業員に作業負荷がかかり過ぎている場合は、人員の配置を見直しや、採用活動の強化などによって、問題の解決を図ることも重要です。過度に仕事を抱えている状態は従業員にストレスを与え、ワークエンゲージメントを低下させる要因になります。
ツールを利用する
ワークエンゲージメントの測定や向上に役立つツールを利用することも有効です。「エンゲージメントツール」「エンゲージメントサーベイツール」などと呼ばれ、独自のテストでエンゲージメントの状態を測定したり、上司と部下あるいは同僚同士のコミュニケーションをサポートしたりできます。エンゲージメントツールは、メーカーから発売されている製品を利用することもできますが、自社の特性に合った形で新しく作成するのもおすすめです。
まとめ
ワークエンゲージメントの向上は、生産性や顧客満足度の向上、離職率の低下など、さまざまなメリットを企業にもたらします。ワークエンゲージメントを向上させるには、職場環境や制度の整備とともに、従業員の心理的安全性を高めるための施策も必要です。本記事を参考に、ぜひワークエンゲージメントの向上に取り組んでみてください。
社内アプリを用いてイキイキした組織を!
近年は社内スマホアプリを開発する企業も急増しています。自社アプリ開発プラットフォームを用いれば、従業員のITリテラシーを考慮した使いやすい自社アプリを開発できます。
どの部署でも自分のスマホから会社の情報に触れられるのは便利ですよね。
「Yappli UNITE」ならノーコードで社内アプリを開発することができ、ビジョン浸透から人材育成、業務効率化までオールインワンで自社のスマホアプリで実現します。ノーコードだからこその、分析で終わらず迅速にアクションまで繋げられる運用も魅力です。
具体的な施策としては、社長・役員メッセージ、デジタル社内報、エンゲージメントサーベイ、プッシュ通知を用いた重要なお知らせ、研修資料・動画、社内FAQなど社内に散らばったコンテンツをスマホアプリ一つにまとめることが可能に!
ぜひ以下よりYappli UNITEでできる具体的な施策や、事例をご覧になってみてください。