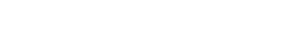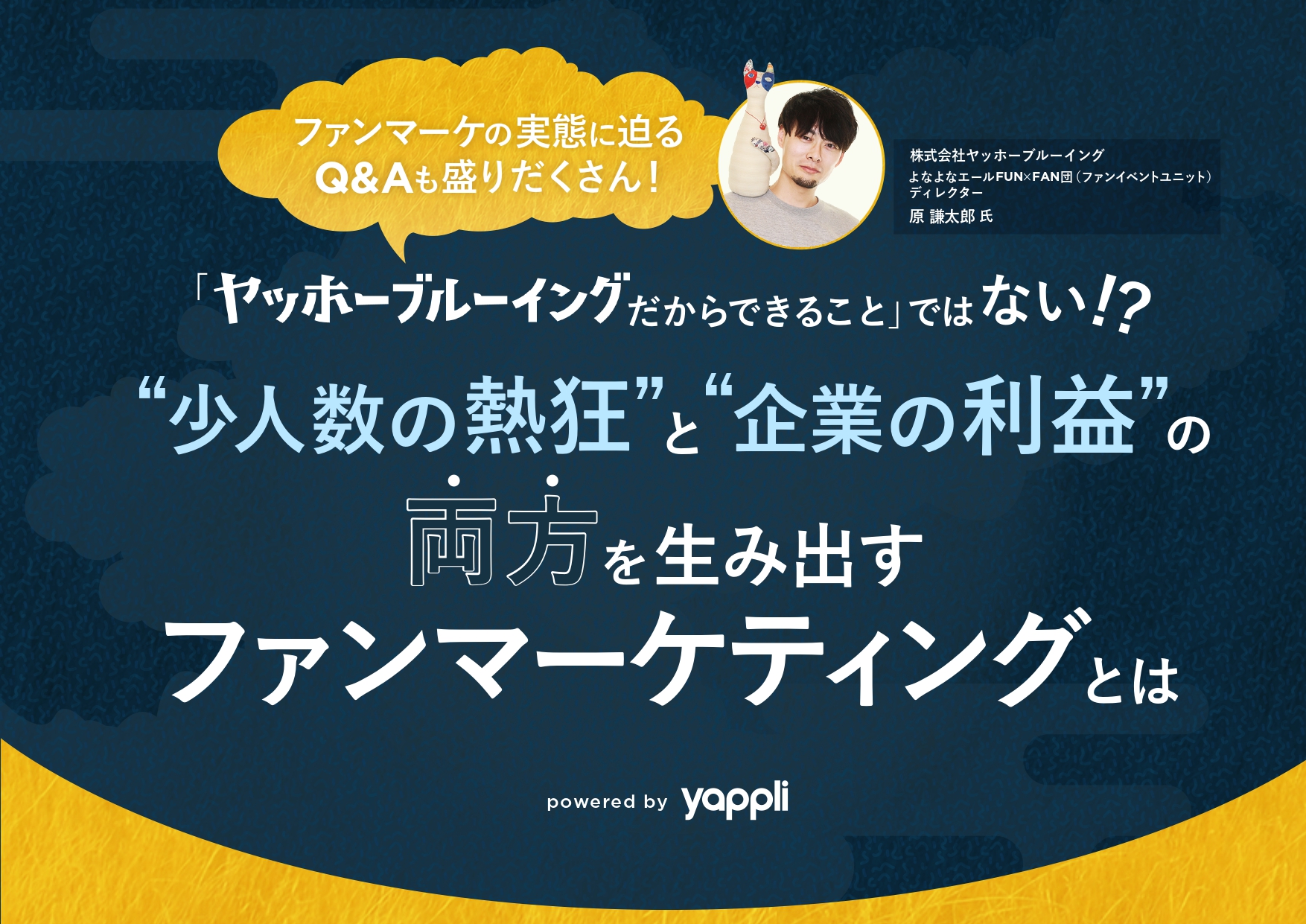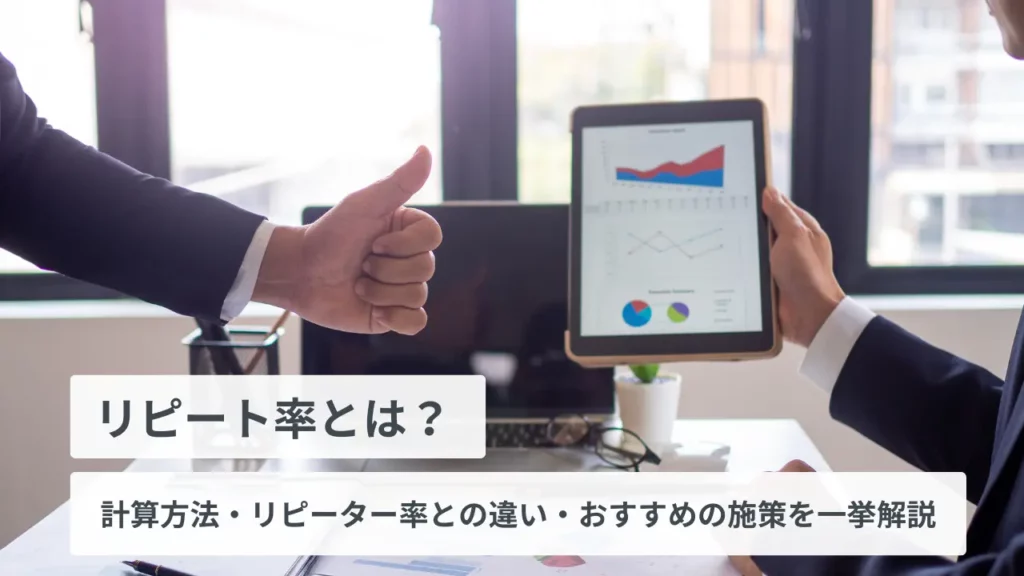
ビジネスにおいて新規顧客の獲得は重要ですが、そのためには多額の宣伝費を投入する必要があります。そのため、売上を上げるためには、新しく獲得した顧客に商品やサービスを買い続け、リピーターになってもらう施策も忘れてはなりません。
この記事では、リピート率の計算方法とともに、顧客に繰り返し購入してもらうことの重要性、繰り返し購入を促す方法をご紹介します。
目次
リピート率とは
既存顧客のリストが与えられたとしましょう。次の1ヶ月、四半期、半期、1年間で、リストのうちの何パーセントの顧客がもう一度購入するでしょうか? リピート率はそうした疑問に答えるための指標です。ここでは、リピート率の意味を顧客ライフサイクルの観点から説明します。
顧客と企業の付き合いは、顧客が宣伝媒体や口コミで企業の商品やサービスに気づくところから始まります。顧客はその後、商品やサービスについて、またそれらを販売している企業についても知ろうとするでしょう。顧客が購入に至れば「新規顧客」となり、新規顧客は商品やサービス、アフターケアなどを経験します。
顧客がそうした経験を経てもう一度購入すれば、「リピート顧客」となります。顧客がリピート購入を続ける間、企業は顧客に対してさまざまな顧客体験を提供します。そしていつか、顧客が購入をやめる日がきます。
企業は顧客ライフサイクルの各段階において、適切な施策を展開する必要があります。リピート率とは、新規顧客のうち何パーセントが、リピート顧客になったかを表します。リピート率が高いということは、初めて購入した顧客を上手く2回目の購入に結びつけていることを意味します。
しかし、顧客ライフサイクルを「初回購入」と「2回目購入」だけで分けるのは、大雑把であると言わざるを得ません。既存顧客へのマーケティングをきめ細かく行うためには、「3回目以上の購入」も顧客ライフサイクルの節目と考えて、適切な施策を行う必要があります。そのとき、初回顧客が3回目の購入に至るリピート率や、2回購入した顧客が3回目に購入する率の意味でのリピート率が設定されます。さまざまなリピート率を見れば、各施策の有効性を確認することができます。
製品・店舗のファンとの関係構築にお悩みの方必見!
昨今、ファンに愛されるブランドを作ることは、短期的に売上を求めること以上に重要視されているポイントです。
ヤッホーブルーイング様は、そんなファンマーケティングの施策を長年にわたって行なっている企業です。
本資料には、そんなヤッホーブルーイング流のファンマーケティングに関する極意をまとめています。サクッと読めるので、ぜひご覧ください。
リピート率の重要性
企業が収益を増やすためには、商品やサービスを顧客に繰り返し購入してもらう必要があります。つまり、企業はリピート顧客を増やす必要があるわけです。リピート率を見ることで、企業のリピート顧客を増やす努力の有効性を測定することができます。
収益向上に大きく貢献する
最初に、リピート客が企業の収益に大きく貢献することを確認しましょう。1回購入するごとの単価が変わらないとすれば、毎月の売上は、毎月の購入回数に比例します。また、ビジネスを始めてから現在までの売上は、それまでの全顧客を対象とした購入回数に比例します。
ここで一人ひとりの顧客に注目しましょう。顧客は企業の商品やサービスを、1回だけ購入して離れることもあれば、複数回購入することもあります。複数回購入する顧客がリピーターです。
全期間の購入回数を、顧客の購入回数に分割して考えることができます。同様に、ある月の購入回数を、顧客の購入回数で分割することができます。ある期間の購買は、初回客による購入、2回目客による購入、というように購入回数で分割することができます。顧客が平均して何回購入するかが分かれば、以下の式を考えることができます。
全期間の購入回数 = 顧客数 × 平均購入回数
すべての顧客は当然、最初は初回客だったので、顧客数は各月の新規顧客数を足し合わせることで計算できます。上の式を見れば、売上を上げるためには、新規顧客を集めることと、繰り返し購入してもらうことの両方が重要であることがわかります。企業の売上は、全ての顧客が1回だけ購入して離脱する場合の売上に、リピート回数を乗じたものになります。
リピート購入を促すためのマーケティングは、新規顧客を獲得するマーケティングと比較して、はるかに効率的です。新規顧客を獲得するためにマーケティングが必要であることと同様に、既存顧客に再度購入を促すためにも、マーケティングが必要です。
顧客を「優良顧客」へと引き上げられているかがわかる
優良顧客とは、繰り返し購入してくれる、常連とも言える顧客です。優良顧客とよく似た言葉に「ロイヤルカスタマー」があります。優良顧客が購入回数を重視した概念であることに対して、ロイヤルカスタマーは顧客と企業の情緒的なつながり、エンゲージメントに着目した概念です。
企業の売上は、優良顧客やロイヤルカスタマーによる購入が主要な部分を占めており、このことを端的に述べたものとして、企業の売上の80%が20%の優良顧客から来るとする「80:20の法則」があります。
リピート率は、初めて購入した顧客の何パーセントが2回以上購入しているのかを示す数値です。長期的に月間のリピート率をチェックすることで、初回客のうち、どれだけが優良顧客に引き上げられているかを判断する指標として活用することができます。
リピート率の計算方法

それでは、リピート率をどのように計算したら良いのでしょうか。「リピート」といっても、2回目購入や3回目購入、前回購入後半年以内の購入など、さまざまな状況があります。また、特定の商品、店舗、購入形態などに限定して考えることもあります。
何を分析したいかに合わせて、最適な手法でリピート率を計算する必要があります。顧客ライフサイクルのどこに注目して施策を実施するのかを明確にした上で、リピート率の算出を行いましょう。
リピート率としてよく紹介される数値は、「月間リピート率」です。月間のリピート率は、前月までに購入した顧客のうち何パーセントが当月に購入するのかを示す指標です。
当月の月間リピート率 = 当月のリピート購入者数 / 前月までの購入経験者数 × 100 %
前月までの購入経験者数は、前月までの毎月の新規顧客数を足し合わせることで算出できます。
また、期間を限定しないでリピート率を計算することもあります。
期間を限定しないリピート率 = これまでに2回以上買ったことのある顧客数 / これまでに買ったことがある顧客数 × 100 %
同様に、2回購入した顧客の何パーセントが3回以上購入するか、などのリピート率を考えることもできます。
「リピーター率」とは?

リピート率と混同されやすい指標に、「リピーター率」があります。何が違うのでしょうか? 以下で解説していきます。
リピーター率
リピーター率とは、購入顧客のうち、何パーセントがリピート客であるかを示す指標です。
月間のリピーター率は、以下の式で計算されます。
当月のリピーター率 = 当月のリピート購入者数 / 当月の購入者数 × 100 %
「リピート率」と「リピーター率」の違い
リピート率は、顧客のうち何パーセントががもう一度購入するかを示す数値なので、上げることが望ましい数値です。リピーター率は、売上全体に対するリピート顧客の寄与を示す数値なので、必ずしも上げるべき数値ではありません。
なぜ必ずしも上げるべきではないのか、説明のためにリピーター率を少し違う形で表現してみましょう。
当月のリピーター率 =
当月のリピート購入者数 / (当月の新規購入者数 + 当月のリピート購入者数) × 100 %
この式から、当月のリピート購入者数が減っていても、当月の新規顧客がほとんどいなければ、当月のリピーター率が100%に近づくことがわかります。この状況は、いわゆる「ジリ貧」であり、ビジネスとして望ましいものではありません。当月の新規顧客数が多いために、当月のリピーター率が低くなる場合は、顧客が1度だけ購入して離脱していることになりますから、これも問題です。
健全な経営のためには、新規購入者と、リピート購入者の両方を増やす必要があります。購入者の絶対数とともにリピーター率を見ることによって、売上を増加させるためのさまざまな施策のうちでどこに問題があるのかを、特定することができます。
リピート率を高めるためには?

リピート率を高めるためには、顧客に繰り返し購入してもらう必要があります。顧客に繰り返し購入してもらうためには、顧客との接点を増やし、企業やブランドに対するエンゲージメントを高めることが必要です。
繰り返し購入してもらうためには、繰り返し購入することが顧客にとってメリットとなるような仕組みの導入も有効です。これまでのデータを分析することで、施策の有効性を確認して、より良い施策を目指して改善を続けましょう。
様々なチャネルで顧客との接点を持つ
さまざまなチャネルで顧客との接点を持つことにより、顧客はブランドや商品、企業に対してより深く関与するようになります。数多くの顧客経験を積み重ねることにより、顧客の企業やブランドに対する親しみの意識、顧客エンゲージメントが高まります。顧客エンゲージメントを高めることは、リピート顧客を増やし、優良顧客を育てるために、もっとも注力するべき課題です。
商品のコモディティ化や大量の情報流通により、いたるところに顧客離れの機会が出現しています。そのような状況の中でも、企業やブランドの感情的な親しみを感じる顧客は、そのブランドを継続的に購入して、優良顧客やロイヤルカスタマーに成長していきます。
リピーターに「得してもらう」仕組みづくり
繰り返し購入することに具体的なメリットを与えれば、顧客はそのメリットのために購入を続けることでしょう。そうした仕組みのなかで、代表的なものはポイントやクーポンです。
ポイントとは、購入の回数や金額に応じてポイントを与えて、次の購入の機会に値引きして使ってもらう施策です。ポイントは次の購入でしか使えないので、顧客は繰り返し購入するように促されます。
クーポンは、購買とは無関係に、その店でしか使えない割引券を発行して購入を促す施策です。クーポンもその店でしか使えないので、繰り返し購入を促します。
販売促進の方法を検討する中で、近年注目度が高まっているのが「自社アプリ」の活用です。
本資料ではアプリを活用することで販売促進につなげる具体的な方法を、事例と併せて紹介しています。ちょっとしたスキマ時間で気軽に見れるボリュームなので、ぜひ一度ご覧になってみてください!
2.SNS広告
高度なパーソナライゼーションによる顧客体験の向上
データ分析技術と生成AI技術の進化により、パーソナライゼーションの精度と範囲が飛躍的に向上しています。単なる「あなたにおすすめ」の商品提案を超えて、顧客一人ひとりの購買パターン、行動履歴、嗜好、ライフスタイルを総合的に分析した高度なパーソナライゼーションが可能になっています。
特に注目すべき最新のパーソナライゼーション手法には以下があります:
- 予測型パーソナライゼーション: AIが顧客の将来のニーズを予測し、タイミングよく提案する手法。例えば、季節変化や過去の購買パターンに基づき、顧客が必要としそうな商品を先回りして提案します。
- コンテキストアウェア・パーソナライゼーション: 時間帯、天候、地域イベント、顧客の現在地などのコンテキスト情報を加味した提案。例えば、雨の日に防水商品を優先表示したり、地域の祭り期間中に関連商品を提案したりします。
- 感情分析を活用したエンゲージメント: 顧客のレビュー、問い合わせ内容、SNS投稿などのテキストデータから感情傾向を分析し、コミュニケーションやオファーを最適化する手法。
最新の調査によれば、高度なパーソナライゼーションを実施している企業はそうでない企業と比較して、リピート率が平均40%高く、顧客あたりの年間購入額も28%増加しています。さらに重要なのは、パーソナライゼーションによって顧客満足度が向上し、ブランドへの感情的なつながりが強化されることです。
▷▷高度なパーソナライゼーションを実現するCRMについて知りたい方は、ぜひこの記事もご覧になってみてください。
既存データを分析し、施策を展開する
さまざまな施策がうまくいっているのかを確認するために、データを分析する必要があります。リピート率の推移をみて、リピート率が急に上がったり下がったりしたときに、なにがあったのか、どのような施策が取られていたのかをみれば、顧客のニーズがどこにあるのか、どのような施策が適切なのかがわかります。
適切な施策はそのまま継続するか、さらに強化します。不適切な施策は止め、問題点を洗い出して改善します。
サブスクリプションモデルの戦略的活用
多くの業界でサブスクリプションモデルが急速に普及しています。このビジネスモデルは顧客との継続的な関係を構造的に確立するため、リピート率向上の強力な戦略となっています。
日本市場では特に、日用品・食品・コスメなどの消耗品カテゴリーだけでなく、アパレル、書籍、電化製品などの分野でもサブスクリプションモデルが拡大しています。2024年の調査によれば、サブスクリプションサービスを導入した企業は平均で顧客生涯価値(LTV)が67%向上し、顧客維持率も従来のリピート購入モデルと比較して3倍高いという結果が出ています。
サブスクリプションモデルを成功させるポイントは、単なる定期購入にとどまらず、以下の要素を組み込むことです:
- 柔軟性の確保: 配送頻度の調整、一時停止、商品の入れ替えなど、顧客が自由にカスタマイズできる仕組み
- 特別な価値提供: サブスクライバー限定の特典、先行アクセス権、独自コンテンツの提供
- 継続的な体験向上: 利用データに基づく商品のパーソナライズ、サービス改善の継続
特に注目すべきは「ハイブリッドサブスクリプション」の台頭で、従来の定期購入に加えて、メンバーシップ特典やポイント還元を組み合わせることで、顧客に複合的な価値を提供する手法が効果を上げています。
自社アプリでリピート率を引き上げへ
自社アプリの活用も、リピート率の引き上げや、リピート客、優良顧客、ロイヤルカスタマーを増加させる有力な手段です。アプリを使って良質な顧客体験を提供すれば、顧客エンゲージメント、つまり顧客の企業やブランドに対する愛着が高まるからです。
モバイルアプリのトレンド
モバイルアプリは単なる購買チャネルからブランドとの総合的な接点へと進化し、リピート率向上の中核的ツールとなっています。最新のアプリ戦略には以下のような特徴があります。
- シームレスなオムニチャネル体験: 実店舗での購入履歴、オンラインでの閲覧履歴、カスタマーサポートとのやり取りなど、あらゆる顧客接点データを統合し、一貫した体験を提供。2024年の調査では、こうした統合されたアプリ体験を提供する企業は平均リピート率が52%向上しています。
- マイクロモーメントの活用: 顧客の日常生活における「知りたい」「行きたい」「買いたい」「やりたい」といった瞬間(マイクロモーメント)に、的確な情報やオファーを提供する戦略。位置情報やコンテキストデータを活用したプッシュ通知の最適化がカギとなります。
- 生成AI搭載パーソナルアシスタント: 生成AIを活用した対話型インターフェースにより、顧客の複雑な質問や要望に応える次世代のカスタマーサポート機能。製品推奨、使用法アドバイス、トラブルシューティングなど多岐にわたるサポートを24時間提供します。
- バーチャルとリアルの融合: AR(拡張現実)/VR(仮想現実)技術を活用した没入型ショッピング体験の提供。特に家具、アパレル、化粧品などの分野で「試してから買う」体験を可能にし、購入の不確実性を低減します。
特に注目すべきは、単一の機能ではなく、ショッピング、サポート、コミュニティ、エンターテイメント、決済など多様な機能を一つのアプリに統合することで、顧客の日常生活の中心的プラットフォームとなりつつあることです。
ノーコードのアプリプラットフォーム
自社アプリの有効性は明らかですが、アプリ開発には時間とコストがかかるという問題があります。
そこでおすすめなのが、スマートフォンアプリの開発実績が豊富な、弊社Yappliです。Yappliは、アプリの開発・運用・分析をクラウドからワンストップで提供するプラットフォームです。
プログラミングは不要。幅広いデザインの高品質なネイティブアプリを短期間で開発可能です。
また、管理画面はブログ感覚で誰もが簡単に更新作業を行うことができます。そのため、専門的な知識は一切必要なく、非エンジニアでも運用可能です。
さらに、申請時のストアサポートや、リリース後のダウンロード施策など、アプリで成果を出すための運用支援もサポート。
リリースから運用まで安心して任せることができるYappli。まずはお気軽に資料請求を!