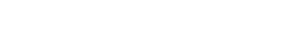リターゲティング広告とは、広告主のWebサイトを離脱したユーザーをCookie情報で追跡し、別のWebサイトやSNSなどに自社広告を表示するWeb広告です。
本記事ではリターゲティング広告の仕組みやメリット・デメリットについて解説するとともに、主な広告媒体や広告費の目安、運用効果を高める方法などを紹介します。
目次
リターゲティング広告とは
リターゲティング広告とは、過去にサイトを訪問したユーザーを追跡し、別のWebサイトやSNSなどに広告を配信する手法です。たとえば車の購入を検討しているユーザーが中古車販売サイトを閲覧した後、別のサイトに遷移しても、中古車の広告が表示されることがあります。この仕組みがリターゲティング広告です。
ユーザーは様々なサイトを閲覧するうちに、条件に見合う商品がどのWebサイトに掲載されていたかを見失ってしまうことがよくあります。リターゲティング広告を表示させることで、そのような見込み客を再び自社のWebサイトに誘導できます。
リターゲティング広告の仕組み
リターゲティング広告は、「Cookie(クッキー)」と呼ばれる機能を活用してユーザーを追跡します。Cookieとは、Webサイトを閲覧したPCなどに、ユーザーの入力データや行動履歴などの情報をブラウザに保存する仕組みです。Webサイトにリターゲティング用のタグを設置すると、サイトを訪れたユーザーのブラウザにCookieを付与することができ、WebサイトやSNSなどの広告枠に自社の広告を表示させられます。
リターゲティング広告のメリット
過去に自社のオンライン媒体を訪れたユーザーに対して広告を配信することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。リターゲティング広告の主なメリットとしては以下の4つが挙げられます。
CVR(コンバージョン率)が高い
コンバージョンとはWebサイトの最終的な目標や成果を表す概念であり、その達成率を「CVR(コンバージョン率)」と呼びます。
たとえば、ECサイトであれば商品の販売、コーポレートサイトならお問い合わせや見積もり依頼の獲得、ランディングページの場合はサービスの申し込みなどがコンバージョンに該当する指標です。
リターゲティング広告は一度Webサイトを訪問したユーザーに広告を配信できるため、すでに自社の商品やサービスを認知している見込み客にリーチできます。
そのため、マス広告のように不特定多数の潜在層に配信される広告と比較してCVRが高いというメリットがあります。
離脱したユーザーを取り戻しやすい
機会損失の最小化もメリットのひとつです。先述した中古車販売サイトの例のように、基本的に多くのユーザーは複数のWebサイトをまたぎながら横断的に商品を比較・検討します。そして自社サイトを訪れたとしても、より良い情報を求めて競合企業のWebサイトへ流れてしまうケースが少なくありません。市場の成熟化とともに差別化が困難となっている現代では、いかにしてこのような機会損失を抑えるかが重要課題です。
リターゲティング広告は一度離脱してしまったユーザーに対して再度アプローチできるため、機会損失を最小化しつつ販売機会の最大化に貢献します。
ターゲティングした層に集中したアプローチができる
広告戦略は「認知度の拡大」と「コンバージョンの獲得」という2つの方向性に分類されます。認知度の拡大には不特定多数の潜在層に対する広範囲なプロモーションが求められ、コンバージョンの獲得にはセグメントされた見込み客への局所的なアプローチが必要です。
リターゲティング広告は、後者のコンバージョン獲得のための広告戦略を展開する上で欠かせない手法です。リターゲティング広告はCookie情報に基づいてターゲットを絞り込めるため、購買意欲の高い見込み客のみに訴求できます。そのため、広告の「無駄打ち」を防ぎ、顧客獲得単価を抑えられます。
リピーター獲得にも有効である
リピーターの獲得に寄与する点も大きなメリットです。
事業活動において新規顧客の獲得は重要課題のひとつですが、新規顧客に対する販売コストは既存顧客への販売コストと比較して5倍の費用が必要です。これをマーケティングの分野では「1:5の法則」と呼びます。つまり、可能な限り低コストで利益率を高めるためには、リピーターの獲得が重要です。
リターゲティング広告はコンバージョンに至ったユーザーに対しても再度アプローチできるため、商品の再購入やサービスの再利用を促進できる可能性が高まります。そしてプロダクトの再認識によってユーザーのブランドに対する愛着が深まれば、既存顧客のロイヤルカスタマー化を促すことができます。
リターゲティング広告のデメリット
さまざまなメリットをもたらすリターゲティング広告ですが、その特性上のデメリットも少なくありません。リターゲティング広告の懸念点や問題点としては以下の4つが挙げられます。
マイナスイメージ
リターゲティング広告はユーザーをCookie情報で追跡し、他のWebサイトやSNSなどの広告枠に自社の広告を繰り返し表示させるWeb広告です。そのため、何度も同じ広告を目にすることでマイナスイメージや嫌悪感を抱くユーザーも少なくありません。ユーザーに不快感を与えることで販売機会の損失を招くのはもちろん、ブランドイメージの低下による顧客離れと収益性の減少も懸念されます。
このような事態を回避するためには、独自性に優れるユニークな広告を作成したり、一人のユーザーに広告を表示する上限回数を設定したりといった対策が必要です。
新規ユーザーや潜在ユーザーには不向き
リターゲティング広告は特定の見込み客に対して、ピンポイントで広告を表示できる点が大きなメリットです。しかし裏を返せば潜在層に対する認知度拡大には不向きであることを意味します。自社のオンライン媒体において何らかのアクションを起こしたユーザーのみに配信される広告のため、自社のプロダクトを認知していない層にアプローチすることはできません。したがって、まずは幅広い層にアプローチできる広告媒体を駆使して見込み客を集め、その上で各ユーザーにパーソナライズされた広告体験を提供するという戦略が必要です。
検討期間が短い商材には向いていない
リターゲティング広告は検討期間が短いプロダクトには適していません。
なぜなら低価格帯の商品や緊急時のサービスといった検討期間が短いプロダクトの場合、リターゲティング広告が表示される前に別の競合サイトで成約に至る可能性があるためです。
たとえば自動車や不動産などの検討期間が長いプロダクトは「自社サイト」→「サイトA」→「サイトB」→「サイトC」→「リターゲティング広告」→「自社サイトで成約」となり得ます。しかし検討期間が短いプロダクトの場合は「自社サイト」→「サイトAで成約」となり、リターゲティング広告がその役割を果たせない可能性があります。
データの蓄積に時間がかかる
リターゲティング広告を効果的に運用するためには、見込み客に関する十分なデータが必要です。たとえばコンバージョンに至ったユーザーは除外する、トップページで離脱したユーザーと申し込み直前で離脱したユーザーで広告を変える、あるいはユーザーの購買意欲によって入札単価を調整するなど、詳細なターゲティングによって効率的な広告戦略を展開できます。
しかし見込み客のデータが蓄積されていなければ、こうした詳細なターゲティングの設定は不可能です。データが不足している状態ではターゲティングの精度が低下するのはもちろん、広告媒体によっては広告出稿そのものができないケースもあります。
リターゲティング広告の種類
リターゲティング広告の主な種類として挙げられるのが以下の6つです。
- 標準のリターゲティング 広告主のWebサイトに訪れたユーザーを追跡し、定義されたセグメントや配信条件に基づいて広告を表示する。
- 動的リターゲティング 標準のリターゲティングに加え、Webサイトの閲覧履歴や行動履歴に基づいてパーソナライズされた広告を配信する。
- 動画リターゲティング 広告主のYouTubeチャンネルや特定のWebページ、動画コンテンツなどを視聴したユーザーに対して広告を表示する。
- 検索広告向けリマーケティング(RLSA) 広告主のWebサイトに訪問した履歴のあるユーザーがインターネットで検索した際に、検索広告をカスタマイズして表示する。
- アプリのリターゲティング アプリをダウンロードしたり、特定のアクションを起こしたりしたユーザーに対して広告を配信する。
- 顧客情報に基づくリターゲティング(カスタマーマッチ) カスタマーマッチと呼ばれる機能を用いて顧客リストを作成し、そのユーザーデータに最適化された広告を配信する。
リターゲティング広告の導入に向いている企業
リターゲティング広告の運用が適しているのは、比較的高単価で検討期間が長いプロダクトを取り扱っている企業です。
たとえばカーディーラーや中古車販売店、デジタルデバイスの製造・販売企業、不動産仲介会社、金融商品取引業者、旅行代理店などが挙げられます。
こうしたビジネスモデルのプロダクトは顧客単価が高く、見込み客は購入までに多数のWebサイトを遷移しながら比較と検討を繰り返すのが一般的です。
その間にさまざまな媒体で広告が表示されれば見込み客の興味関心や購買意欲を醸成できるため、ユーザーを再び自社のWebサイトに誘導できる可能性が高まります。
リターゲティング広告の費用
リターゲティング広告の課金方式は大きく分けると「クリック課金」と「インプレッション課金」があります。
クリック課金は表示された広告がクリックされた回数に応じて費用が発生する課金形式です。
インプレッション課金は広告が表示された回数によって費用が発生する課金形式で、一般的に広告表示1,000回に対して課金されます。
広告媒体や入札価格によって変動するので一概にはいえませんが、クリック課金は1クリックあたり50〜100円、インプレッション課金は1,000回表示あたり10〜500円程度が広告費用の一般的な相場です。
リターゲティング広告の主な媒体
リターゲティング広告を運用できる代表的な広告媒体は以下の3つです。
Google / GDN
「GDN(Google Display Network)」とは、Google広告で出稿するディスプレイ広告です。
ディスプレイ広告は検索結果の上部や下部などに掲載される検索広告とは異なり、WebサイトやSNS、アプリなどの広告枠に掲載されます。ターゲティングのオプションを幅広く設定することで不特定多数の潜在層にアプローチできるのはもちろん、Cookie情報やカスタマーマッチに基づくリターゲティング型の広告配信も可能です。
広告が配信される主な媒体としてはYouTubeやGmailのようなGoogleのWebサービス、Google AdSenseを利用しているWebサイト、またはlivedoorやgooといったパートナーサイトなどが挙げられます。
Yahoo / YDA
「YDA(Yahoo Display Ads)」とは、Yahoo!JAPANが提供するディスプレイ広告です。基本的にはGDNと同様の広告配信機能を有しており、ユーザーの年齢や性別、居住地、職業、家族構成などのデモグラフィックデータに基づいて広告配信を制御できます。
そしてGDNと同じくリターゲティング広告の配信も可能です。YDAはYahoo!ニュースやYahoo!知恵袋、Yahoo!ショッピングなどのYahoo!JAPANが運営するサービスサイト、またはLINEや朝日新聞などのパートナーサイトなどに広告が配信されます。
なお、GDNは「リマーケティング広告」、YDAは「リターゲティング広告」と呼ばれますが、呼び名が異なるだけでほぼ同義の概念です。
SNS広告
SNS広告とは、ソーシャルメディアのプラットフォームに表示される広告です。
SNSのタイムライン上やトークリスト、ニュースコンテンツ、SNSアプリの起動時、動画コンテンツの合間などに広告が表示されます。
GDNやYDAと同様に不特定多数のユーザーにアプローチできるのはもちろん、セグメントされたユーザーに対するリターゲティング広告の配信も可能です。SNS広告の配信機能をもつ代表的なソーシャルメディアとしては以下の4つが挙げられます。
Facebook広告はFacebookのストーリーズやフィードなどに出稿できるSNS広告です。
Facebookだけでなく、InstagramやMessenger、Audience NetworkといったMeta社が運営するさまざまなプラットフォームに広告を配信できます。Facebookは基本的に実名登録制のソーシャルメディアであり、多くのユーザーが詳細な個人情報を入力するため、データに基づく精度の高いリターゲティング広告を展開できます。
また、Facebookは若年層の利用率こそ低いものの、30代や40代のユーザーが多い傾向にあります。そのため、Facebook広告は中年層をメインターゲットとするビジネスモデルに適したSNS広告です。
X(旧Twitter)
X広告はXのタイムライン上やおすすめユーザー欄、検索結果などに表示されるSNS広告です。Xは匿名性が高く気軽に情報を発信できるSNSであり、他のソーシャルメディアよりも情報の拡散性に優れるという特性を備えています。基本的に二次拡散は課金対象外となるため、最小限の広告費で数多くの潜在層にリーチできる可能性を秘めているのがX広告の特徴です。
また、XはFacebookとは対照的に10代や20代のユーザーが多いため、若年層へのアプローチに適したSNS広告です。ただしGDNやYDA、Facebook広告などと比較するとターゲティングの精度は劣る傾向にあります。
Instagram広告はInstagramのフィードやストーリーズ、発見タブなどに出稿可能なSNS広告です。Instagramは10代や20代の若年層に絶大な人気を誇るソーシャルメディアであり、とくに女性ユーザーの比率が高いのが大きな特徴です。
そのため、若年層をメインターゲットとするプチプラコスメやアパレル系のビジネスモデルに適しています。また、Instagram広告はデモグラフィックデータだけでなく、ユーザーの興味関心や行動履歴に基づく詳細なターゲティングができるのも大きな特徴です。
たとえばターゲットをファッションやフィットネスに興味関心の高い20代の女性に絞り込み、該当するユーザーのみに広告を配信するといったターゲティングができます。
LINE
LINE広告はLINEアプリ内のトークリストやLINE VOOM、LINE NEWSなどに表示されるSNS広告です。LINEは国内の人々にとって必須の通信インフラといっても過言ではなく、2023年3月末時点で月間9,500万人(※)のユーザーが利用しています。FacebookやTwitterなどは利用しないものの、LINEは使っているというユーザーも多く、あまりSNSを活用しない層にアプローチできる点がLINE広告のメリットです。
また、年齢や性別を問わず利用されているLINE上に広告が配信されることで、不特定多数のユーザーに対する認知度の向上が期待できます。もちろん広告主のWebサイトを訪問済みのユーザーに対するリターゲティング広告の配信も可能です。
(※)参照元:LINE広告の特長とは?配信面や費用、導入事例を総まとめ|LINE for Business
リターゲティング広告の効果を高める方法
リターゲティング広告の運用成果を高めるためには、蓄積されたユーザーデータに基づく詳細なターゲティングが求められます。
たとえば成約率の低い流入元からのユーザーは除外する、ユーザーの離脱ポイントに応じて広告を出し分ける、あるいは一定の検討期間を過ぎたユーザーを除外するなどです。
サイトの離脱直後ではなく検討時期に入ったユーザーに配信するなど、配信時期の見極めも必要です。こうした詳細な設定によって購買意欲の高いユーザーのみに広告を配信できれば、CVRの向上と費用対効果の上昇が期待できます。また店舗型のビジネスを展開している企業であれば、特定の地域に居住しているユーザーのみに広告を表示するなどの工夫も有効です。
リターゲティングは規制が進んでいる
Cookieはリターゲティング広告の基盤となる技術ですが、個人情報の漏洩を懸念する声が少なくありません。
国内では2017年と2022年に改正個人情報保護法が施行され、2018年にはEUで「GDPR(EU一般データ保護規則)」が、2020年には米国のカリフォルニア州で「CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)」が施行されるなど、世界各国でCookie規制が加速しています。
すでに一部のWebブラウザではサードパーティCookieがブロックされる仕様になっており、今後もその動きは加速していくと予測されます。
Cookieの規制によってユーザーの閲覧履歴や行動データを追跡する機能が制限されれば、精度の高いターゲティングや効果測定は困難です。Cookie規制が進む現代では、いかにしてファーストパーティデータを活用するかが今後のマーケティング戦略における重要課題となります。
関連記事:ファーストパーティデータとは? 活用方法や収集方法などを解説
まとめ
リターゲティング広告はWebサイトを訪れたユーザーを追跡し、別の媒体に自社広告を表示するWeb広告です。離脱したユーザーに広告を表示することで自社サイトに再び誘導できる可能性が高まります。しかし規制が進んでいるため、サードパーティCookieに依存しない広告戦略の立案やアプリの戦略的活用が必要です。