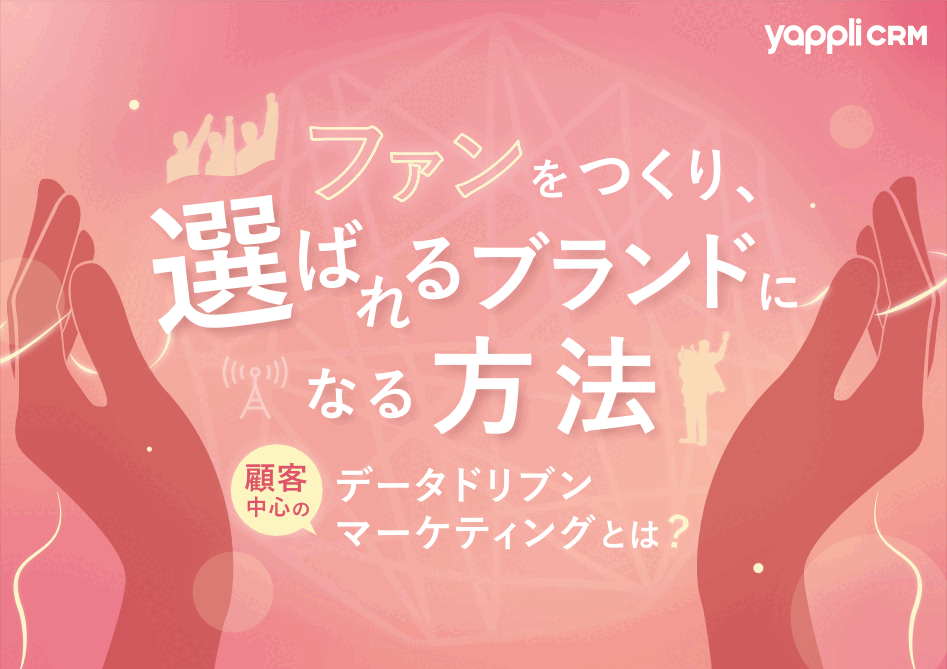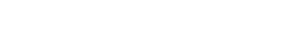この記事のテーマは、「コンテンツマーケティング」。企業が伝えたいことありきではなく、読者が求める情報を起点にコンテンツをつくり、長期的な視点で顧客を獲得するという考え方・手法で、多くの企業が自社メディアを持ち、様々なストーリーを発信しています。しかし、コンテンツマーケティングで優れた結果を出した企業もある中で、思ったように結果が出ず、自社メディアを畳むケースも目立っており、一部では「自社メディアはオワコン」という声も上がるほど。成否の分け目となる要素は一体何なのでしょうか?
そこで今回は、ホームセンターのCAINZが手がけるWebメディア「となりのカインズさん」の副編集長を務める与那覇一史さんをゲストに招き、“シン・オウンドメディア論”というテーマで、優れたコンテンツをつくる秘訣やKPIの考え方、コンテンツマーケティングと売上の関係などについて、根掘り葉掘りお聞きしました。
前編では主に、本メディアを運営する株式会社ヤプリが2022年8月30日に実施したオンラインセミナー「廃れる自社メディアには理由がある!?カインズ副編集長が語るシン・オウンドメディア論」の内容をお届けしました。後編では、セミナー終了後のアフタートークとして、ヤプリのマーケティング担当がセミナーを見て抱いた更なる疑問を1時間半にわたって与那覇さんにぶつけてみた様子をQ&A方式でお届けします。セミナーをご覧になっていただいた方にとっても、オウンドメディアへの理解がより深まる内容となっていますので、ぜひご覧ください。
>>前編はこちら
GUEST PROFILE

与那覇 一史 株式会社カインズ マーケティング本部 メディア戦略部 グロースグループマネージャー
美術専門出版社の営業職を経て、株式会社キュービックでメディア運用に従事。その後、体験ギフトのソウ・エクスペリエンス株式会社でECサイトのグロースを経験。趣味のメダカ・ミジンコ・SEO・縄文時代・ゾウリムシ・家庭菜園・読書・カブトムシを相棒に「おもしろいコンテンツとは何か?」を常に考えている。人生のテーマは観察と分析と実行。
販促 or ブランディング?与那覇さんの考えは…
まずは、ペルソナに対する考え方や、販促目的のコンテンツとブランディング目的のコンテンツのどちらを重視すべきかといったことをお聞きしました。
Q.となりのカインズさんではどのようにペルソナやターゲットを定めているのですか?
A.となりのカインズさん全体でのターゲット像もあるにはありますが、あまりそれを強く意識しているわけではないかもしれません。それよりも、各コンテンツごとに想定読者について深く掘り下げることの方が多いですね。オウンドメディア全体としてのペルソナ像を明確化することで、作るべきコンテンツの方向性がはっきりしやすくなると思いますが、その分、コンテンツの幅が狭まってしまうリスクも起こりやすくなると思っていて。となりのカインズさんでは、コンテンツの多様性を大切にしているので、メディア全体というよりも個々のコンテンツごとの読者像を重視しているんです。
ありがたいことに、最近は他媒体のWebメディアを担当していた方も何人か転職してくれたのですが、中には20代中頃という若い方もいるんです。その方が考える企画はまあどれも面白いのですが、ホームセンターのお客さまは50〜60代の方も多く、その層の関心ごとと20代が考える企画が重なり合う部分はどうしても少なくなりがち。
メインの顧客層のニーズに合わないならその企画はボツとなりそうなところですが、企画者の熱量とかフェチの度合いが強いのであれば、編集部はGOサインを出します。
個人的に、デイリーポータルZさんというWebメディアが大好きなのですが、もしデイリーポータルZさんが今後全てのコンテンツにおいて“セールス”の姿勢が強く出ているものにしたとしたら、大なり小なり読者は減ってしまうと思うんです。「これ、誰の参考になるんだろう」とつい思ってしまうおバカな(褒め言葉)コンテンツを全力で作っているメディアだからこそ、たまに紹介されている広告要素が強いコンテンツでも読み応えがあるし、信頼できる。
セールス色が強いコンテンツを否定しているわけではありません。ただ、そのようなコンテンツを見てくれる人々のパイは決して大きくはなく、シェアもされにくいと思うんです。なので、まずはコンテンツをセールスと絶対に紐付けないといけないという考えを一旦脇に置いて、作り手のフェチをベースに、より人々に深く響くようなコンテンツづくりをしてみる。そうしてメディアに対する信頼感を醸成できれば、セールス色が強いものも結果に繋がりやすくなると思います。
Q.セールス色が強い、つまり販促目的が主なコンテンツと、ブランディングを目的としたコンテンツについて、どっちを作れば良いのかと悩む担当者は多いと思うのですが、与那覇さんはどのようにお考えですか?
A.私としては、どっちか、ではなく、どっちも、だと思っています。どちらか一方がより重要ということではなく、どちらもオウンドメディアには必要ではないでしょうか。ちなみに、販促目的のコンテンツとブランディング目的のコンテンツは、決して相反するものではなく、例えば販促目的のコンテンツでもブランディングに寄与するほど面白いものだってできると思うんです。なので、どちらの視点も持ちつつ、熱量を込められる企画を考えるのが良いかもしれませんね。
Q.似たような話で、SEOを重視する記事としない記事についてのバランスはどう思われますか?
A.例えば、全ての記事を検索順位で1位にするとしたら、そのメディアのPV数が年間でどのくらいになるのか、そのうちコンバージョン率はどの程度で、売上はどのくらいになるのかって、理論上は出せると思うんです。このペースで行くと3年後、5年後はこのくらいになるというものを出した上で、その数字に合格点が出せるならSEOを重視する記事に重きを置けばいいと思います。
なお、となりのカインズさんの場合は、カインズ全体として掲げている「IT小売企業宣言」の旗振り役として存在しているので、SEOベースの試算結果にとどまらない、何か突き抜けるような結果を出したいよねということで今のようなスタイルになっています。
どうしても自社メディアに熱量を見出せない時は
次に、セミナー本編でもよく話題に挙がっていた、コンテンツに対する“熱量”に関してお聞きしました。
Q.例えば他部署から「この商品やサービスを紹介して欲しい」といった要望がきた際に、なかなかその商品やサービスを絡めた企画に熱量を持たせられない場合はどうすれば良いですか?
A.となりのカインズさんの場合なら、どうしても熱量を出せないとなったらお断りさせていただきますね。ありがたいことにカインズ社内でもとなりのカインズさんをもっと活用したいという声をよくいただきますし、この質問のようなパターンもあります。無下に断るということではなく、よく編集部で考えた末の判断なのですが、せっかくとなりのカインズさんと連携したいという相談なわけなので申し訳ない気持ちにはなります。ただ、なんでもかんでも無条件に引き受けてしまうと、メディアの軸がブレてしまうリスクが高まるので、コンセプトに合った内容にできるかどうかはよく吟味しています。
ちょっと話はズレるんですが、コンセプトってすごく重要だなと感じていて、“ホームセンターを遊び倒すメディア”でなかったら、おそらくとなりのカインズさんもここまで成長できていなかったと思うんですね。オウンドメディア運営で大切なのは、単純に商品やサービス認知を高めるということではなく、読者の関心を呼び起こすことだと本編でもお話しましたが、“遊び倒す”という考え方によって従来の商品説明にとらわれない様々な訴求スタイルを見出すことができたから、関心の呼び起こしもしやすくなっているのかなと。
仮に新しいメディアを作るとして、その場所を祭りと定義するのか運動会と定義するのか、学校と定義するのかによって、伝わり方はまるで変わってくると思うので、コンセプトって大きな存在だなと改めて思いますね。もし、今運営されているメディアのコンセプト的に、あまり熱意を込められなさそうであれば、まずは1記事でも良いから、なるべく熱意を注ぐことができるコンテンツ作りを実験するのが良いかもしれません。いきなりコンセプトをガラッと変えると、これまでの読者さんもびっくりしてしまうと思うので、徐々に全体の方向性を変えていくのはアリだと思います。
Q.そもそもオウンドメディアの立ち上げや運営そのものが、会社の上層部などからミッションとして与えられたもので、担当者としてそこに熱量を見出せない場合はどうしますか?
A.企業によってはそういったケースもあると思いますが、悩ましいですね。私だったらどうするかな…、本編でお話した「オウンドメディアは不要である」論に立ち返るかもしれません。なぜメディアを立ち上げる必要があるのか、何を成し遂げたいのかということを確認し、獲得できそうなPV数やコンバージョン数などをひとまず試算してから、代替案も提示しつつ「本当にやる?」ということをすり合わせる気がします。代替案を出すのはオウンドメディア不要論、つまりオウンドメディアありきの話ではないということで、例えばWeb広告で同じ金額かけた時の想定流入数などと見比べて、最終的にどうするかを詰めていくみたいな。
オウンドメディアは資産になるから、とりあえず始めればいいという論調もありますが、本当に資産となるものはそれこそ企画者やクリエイターの熱意や愛情が込められたものだと思うので、やはりこの部分で難しければ他の方法を考えるのが良いかもしれませんね。企業それぞれの事情はあると思いますが、とりあえず始めたメディアは得てしてコンセプトや目的がぼんやりしてしまいがち。なので、仮にそこそこのPVが取れるようになったとしても、大きな爆発もなく、あまり長くは持たないメディアになってしまう可能性があるので要注意ですし、この失敗パターンが巷では多いがゆえに、今日のオウンドメディアはオワコンという風潮に繋がっているように思います。
Q.試算の話で言うと、SEOベースなら出しやすい一方で、となりのカインズさんが企画されている熱が高めのコンテンツに関する試算は出しにくいと思うのですが、社内合意を得るために何か工夫されていることはありますか?
A.あまり小手先のテクニックはなく、もうただただ、勇気を出すということですね(笑)。となりのカインズさんでは試算しづらいコンテンツをよく企画していますが、最終的にそこへ投資しようと決断するにはとても勇気が要ると思います。熱量が大事と幾度となくお伝えしていますが、私自身はカインズに入る前はSEOでしっかり結果を出すような記事を主に制作しており、一日中分析ツールとにらめっこしていても全然苦じゃないタイプの人間なので、つい数字に引っ張られちゃうんですよ。
ただ、編集長の清水がよく言うのは「PVを追うことで、PVに嫌われないように」と。どういうことかと言うと、例えばとあるテーマパークで仮に入場者数が落ち込んでしまったとして、だからといってテーマパークの最寄り駅とかでスタッフさんがガンガン呼び込みをしていたらちょっと嫌じゃないですか。それと同じで、試算もしやすく、てっとり早くPVを稼げるようなコンテンツって、やりようによっていくらでもあると思うんです。ただ、そうではなく、例えそれがどのような結果を出すか未知数だとしても、腹をくくって、熱意を込められるものを作る姿勢を貫けば、次第に社内合意も得やすくなっていくと思います。

与那覇さんの熱量が特に詰まっているのが「メダカコンテンツ」。となりのカインズさんの検索機能でぜひ「メダカ」と調べてみてください。濃厚なこだわりが詰まった記事が続々と現れます。
手法に溺れる。そうすると、スベる
最後に、コンテンツ作りに関するルールや、“うまくいかないバズ狙い記事”あるあるなどについてお聞きしました。
Q.セミナー本編にて、1日1本ペースで記事を公開しているとおっしゃっていましたが、以前からずっと変わらぬペースなのですか?
A.いえ、私が入社した当時は1日に2〜3記事公開していたので、1日1本がメディアとしての鉄の掟というわけではないですね。編集長の清水が言うのは、例えば公開するコンテンツが月1本とか、あるいは半年に1本でも構わないと。どういうことかと言うと、例えばコンテンツ作りに月100万円をかけられるとして、1コンテンツ10万円で10本作るのと、予算全て1本に注ぎ込んだ時にどのような違いが生まれるのかを見たいんですね。つまり公開する頻度や、1コンテンツにかけるコスト配分に関する実験を常々しており、もしかしたら今後は1日1本ペースからまた変わるかもしれません。
Q.編集部のスタッフ一人あたり月に何本公開するといったノルマはあるのですか?
A.いや、ありませんね。なので、月に10本公開しているスタッフもいれば、その月には1本も公開していないスタッフもいたりして、その裁量は個々人に任されています。
Q.となりのカインズさんには社外のライターさんが多く参加している印象があるのですが、ライターさんはどのように探しているのですか?
A.私のやり方ですと、TwitterなどのSNSで日々探していて、気になる投稿をしている方がいたらDM(ダイレクトメッセージ)をお送りしたりしてますね。その際はあまり文章の良し悪しは気にしていなくて、投稿の内容を見ています。
Q.となりのカインズさんでは文章上の表記ルールについてどのくらい細かく取り決めているのですか?
A.表記ルールもそうですし、記事構成や文章作りにおける一般的なセオリーってあると思うのですが、あまりガチガチにしてしまうと書き手の個性や勢いが消えてしまうので、となりのカインズさんではそこまで意識していません。
Q.いわゆる“バズ狙い”のコンテンツは様々なWebメディアでよく見られますが、これは面白いと思うものもあれば、これはどうかなと思うものもありますよね。与那覇さんが思う、ちょっと残念な“バズ狙い”のコンテンツにありがちなことって何かございますか?
A.マニアックなジャンルの魅力を紹介するために、その道の達人にインタビューをするような記事構成ってよくあるじゃないですか。その際に、達人の方の熱さを伝えるために、インタビュアーが達人の話についていけなくなって引き気味のテンションになっている表現がなされているパターンもよく見かけると思うんです。「なるほど、わからん」みたいな。この手法そのものが悪いわけではないのですが、一つの記事であまりに頻繁に使われていると、コンテンツとしてはちょっと逃げているなと感じてしまうかもしれません。
もし本当に達人のヒートアップした会話についていけなくなったとしたら、素直についていけなくなりましたと伝えて、もう少し噛み砕いてもらうとか、聞き手なりの解釈をぶつけてみるとか、そうやって会話を発展させることもできるはず。そういう試みをあまりしないままに話題作りを狙うと、どうしても巷の手法を乱発してしまいがちになるので、私自身、そうならないように意識しています。
あとは、てっとり早くPV数などを稼ぐために、“〇〇のコツ10選”みたいな、いわゆるまとめ記事もよく見かけると思うのですが、これも個人的にはどうなんだろうと思います。この手法が適しているテーマもあるとは思うので、全てを否定するわけではありませんが、なんでもかんでもこの構成に落とし込まれていると、読む側のテンションは下がってしまいそうだと感じています。要は、手法に溺れることなかれ、ということかなと思います。
本編&アフタートーク合わせて3時間以上にわたり、となりのカインズさん副編集長の与那覇さんとトークした模様をお届けしました。自社のオウンドメディア運営でお悩みの方や、多くの読者の心に刺さるようなコンテンツ作りをしたいと思っている方のヒントになれば幸いです。
この記事をご覧の方へのおすすめ無料eBook!
近年、多くの企業が関心を抱いている「ファンマーケティング」。新規顧客をリピーター、ファン化に繋げるにはどうすればいいかと悩んでいるマーケティング担当者は少なくありません。顧客をファンへと育むためには、顧客について深く理解する必要があり、そこで有効活用したいのが「顧客データ」です。そこで、データを使ってどのように集客やマーケティング施策に活用していくかについてまとめた無料eBookをプレゼントします!ちょっとしたスキマ時間で気軽に見れるボリュームなので、ぜひ一度ご覧になってみてください!